抜け道 (23)
彼は若い男になって、オートバイにまたがっていた。ほとばしる精気が体中にみなぎり、白い光の線を描き彼は走った。周囲はどこまでも紫苑の咲く野であった。
彼の体はいきなり地上に投げ出されていた。曇った空が見えた。人々の話し声がした。今ではそれは、彼に何の意味も伝えなかった。
ただ子供の頃にそばで聞いた川の流れのようにきらきらと耳元を流れていくばかりだ。
彼はひやりとする。ジャンプして飛び越えるべき、大きな溝などもともと存在しないのかもしれない。
それぞれの人間に、それぞれの抜け道がある。変だ、変だと思いながらそれをたどっている。これからもその生をつないでいくことを考え、彼は愕然とする。
セミの声が高くなる頃には、妻は夕方から宵にかけて、白い花の浮き出た藍色の浴衣を着て、若い女のするような朱色の帯を締め、二間続きの座敷の奥にひっそりと座っていた。その年は秋の虫が鳴く頃にもそれを脱がなかった。
――おい。
ある日、いきり立った声で妻が彼を呼んだ。
――見舞いに行くから、急いでタクシーを呼んで。早くしないと、間に合わないだろ。
「どうだい、そろそろ病院に入れることを考えてみたら」
母親がぼそぼそした声でいった。
けれども、それからいくらもしないうち母親のほうが、卒中で亡くなった。妻は戦前から商売をしていた家の娘で、十三歳年上の姉に育てられたから、彼の母親を慕い、葬式を済ませた後も「おかあさーん、おかあさーん」と呼んで家の中を探して歩いた。
亡くなる少し前頃から、何もない座敷の真ん中によく置物のように座っていた。
妻はいきなり立ち上がると、つかつかと彼の側に近づいてきて、ていねいに頭を下げた。
「ちっとも、お見かけしませんで」
「・・・・・・」
「主人でございますか、それならだいぶ前、死にましてございます。お陰さまで、式も滞りなく・・・・・・」
彼は妻の細い手首を握った。
「じゃ、いったい俺はだれなんだ」
「あなたさまですか、あなたは、あたしの、いい人でございますよ」
にっこりと笑いかける妻の、薄青がかった瞳の奥に映る男の姿を、彼は汗ばむ思いで見つめていた。
染め上げた髪をりゅうと結い上げ、襟足はいつも垢じみていた。
どんなにじたばたしても、まともな様子だった妻の姿は浮かんでこない。少女か、狂った女。彼にはそのどちらの姿もいとおしいのだ。









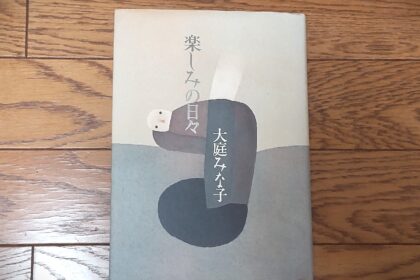
コメントを残す