抜け道 (19)
嫁さんの話は切れ目がない。彼は、うん、うん、と聞いている。ばあさんのほうも彼の家にやってくると、嫁さんの悪口を並べ立てるから、おあいこなのだ。
昼間は二人連れだって、めかし込んで出かけることもあり、実際仲がいいのか悪いのか、わからないのである。嫁さんはふいに、うふふと笑った。
「おじーちゃん、今日、遠藤さん来てたでしょう。いい方でほホントよかったですね。やっぱり、あたしのいったとおりでしょう。なんでも頼んだ方がいいんですよ。無理して自分でやることありませんよ」
彼の目の中に急に背中をこごめ、受話器に向かって陰気に話している遠藤菊子のひっつめ髪の後ろ姿が浮かんできた。それを不思議なもののように思った。この次も菊子はやはり、電話をするだろうか。そして彼はそれを察して散歩に出るだろう。頭にハンチングを被り、坂道を下って、その辺を二、三十分もぶらついてくれば十分だ。
彼がぼんやりして、返事もしないでいるうち、嫁さんは帰ってしまった。
業界紙がだめになったあと、弟は二年ばかりも戻ってこなかった。ある日ふらりとやってきて、そのまましばらく家に居着いた。奥の四畳半の小部屋にいて、午後に出かけ、深夜か明け方に帰宅するという生活だったから、彼と会うことはほとんどなかった。朝、玄関から出るたび、弟の顔が頭の奥にちらりと浮かんだ。
そんな日が十日も続いた後、弟はまた忽然といなくなった。
「あれで、やっぱり居づらかったんだろうね」
夜帰宅した彼に、母親はいった。
「あんたに、よろしくっていってたよ」
その夜、彼は手酌で少し飲んだ。鮎を一匹焼いた。それを食卓にのせる際、妻の白い手が目の前にちらついた。酔いは急速に訪れた。彼は早々に布団を敷き横になった。けれどそうなるとかえって目がさえてしまって眠れない。
その時どこかで、軽いハエの羽音のようなものを聞いた。彼は目を開けて暗い闇の奥をすかして見た。もちろん、何もみえやしない。低いモーター音のようでもある。
隣家の主婦が早くもクーラーをつけ始めたのだろうか。だとしたら八十になるばあさんが、電気代がもったいない、と文句をいってるにちがいない。けれど目を閉じると、やはりそれは、ぶーんというハエの飛びまわる音だった。









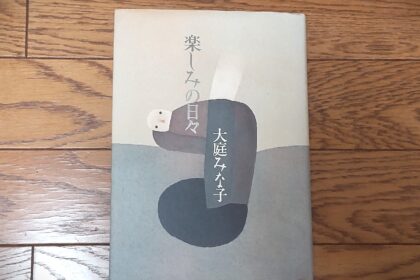
コメントを残す