ツグミ団地の人々〈二人の散歩15 了〉
その夜、疲れていたので彼らは早く布団に入った。
彼はいつもの癖で息子のことをぼんやり考えていたのだが、しばらくして妻が口にしたのはまったく別のことだった。
「ダイヤモンドは傷つけられないって本当かしら」
「ああ、本当だろう」
彼は、昼間街中で見た男の少々芝居がかった口ぶりを思い出しながらいった。
「そうかしら。あたしは違うと思うわ」
「ほーう、どうしてだい」
少々眠くなっていたので彼はぼんやりした口調でいった。
「硬いものはもろいの。一度壊れたらあっという間だわ。本当に傷つかないのは、柔らかいものなのよ」
「そうかい?」
「傷つけられたように見えても、またすぐに元通りになるの」
「ふーん」
「戻る力があるんだわ。だから、あたしも、あなたも生きてられるのよ、隆史もね・・・・・・」
彼は遮光カーテンの隙間から見える団地の家々のぼんやりした明かりに目をやりながらいった。
「そうだな・・・・・・」
しばらくして、澄子の声がしないのに気がついた。
「おい」
彼はとなりに横になっている妻の肩に手をおいた。そして揺さぶった。
きっと、さっきのようにいきなり笑い声をあげるに違いない。けれども妻はぴくりとも動かない。「おい、おい」。何かの冗談だろう、そう思って、心臓のあたりまさぐるが鼓動がするようではなかった。まさか、妻は死んだのだろうか。
いや、いや、じっとしていたら、そのうち起き出すだろう。彼はむしろ落ち着いて横になっていた。こうしていると、二人ながら夜の闇の中に吸い込まれていくようである。窓の向こうにだけ団地の灯がちらちらと見えるのが嘘のようだ。
しばらく寝たかもしれない。
やがて頭の上のほうが明るくなって明け方になったのを知った。でも彼はまだそのまま妻の横にいた。妻の体はもう冷たくなっていた。それでも彼はそのまま隣に横になっていた。
そして陽が差して朝になってもそのままいて、やがて腹が減ったので起き上がると炊飯器から飯を茶碗によそい、茶を注いで茶漬けにして食べた。茶碗を流しで洗うとすることもなかったので、また妻の横に座り、やがていつの間にか隣で眠っていた。
眠りの中で彼は前を歩き、妻が後ろをついてくる。それを感じながら前を向いて歩いていた。彼の鼻はすでに曲がっていた。後ろを振り向けば、わずかに微笑んだ妻の顔はみずみずしいほどの美貌だ。口の横には血痕のような小さなあざがある。それを確かめるとまた、まっすぐ前を向いて歩き始めた。
カツカツ、カツカツ。妻の足音が後ろからついてくる。彼はその音を聞きながらさらに深い森の奥へと入っていった。
了







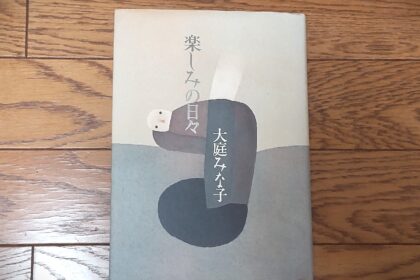



コメントを残す