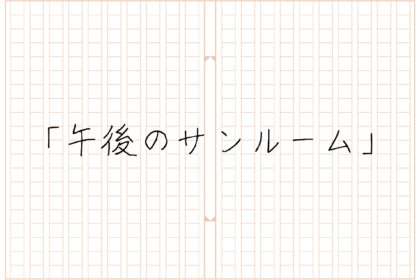ツグミ団地の人々〈二人の散歩4〉
時計の針が八時を指すと、彼らはウォーキングシューズをはいて外へ出る。
今日は月に一度、澄子が病院に行く日に当たっている。彼らは玄関を出ると、ゆっくりと歩き出す。彼が先、妻があとだ。外出した際に、妻が彼のあとしか歩けなくなったのは一年ほど前からだ。それが病気のせいなのかほかの理由からなのか、彼にもよくわからない。
五月の空は、群青色といっていいほど晴れわたり、何かの花の甘い匂いがあたりに満ちている。
「病院はイヤだわ。長くかかるの」後ろから妻が話しかける。
「午前中いっぱいくらいだろう。そのあと、昼飯を食べよう」ふり返らずに彼が応える。
「それがいいわ」
しばらくの間、無言がつづく。ざくざくざく。彼が前、妻が後ろだ。
「今日こそ、寄りましょうね、あの子の所に」
「そうだな。だいぶご無沙汰だからな」
「あ」
「どうした」
「あの子の顔が、どうしても思い出せない」
「何、そのうち思い出すさ」
そうは言ったものの、彼自身、息子の顔をうまく思い描くことができない。白くむくんだような輪郭は浮かんだものの、どんな表情で自分を見つめるかなど、息子の顔の核心にたどりつけない。
彼は、もどかしい思いで道の小石をけった。後ろで妻が、きゃ、と叫ぶ。彼は木の名前も知らないが、人の顔も覚えていることができない質だ。それでは、あの男の顔はどうだったろう。それが不思議なほどよく覚えている。鼻の曲った男の顔。なぜか彼は自分の鼻に触って確かめてみずにはいられなかった。
急にうっすらと日が陰り、曇った五月の空が寒々しくあたりをおおいつくしていた。彼らは、顔をしかめて再び歩き出す。彼が前、妻が後ろ。いつも変わらない。
妻はひどく寒がりで、五月の声を聞いてもまだウールのコートをはおり、長いフレアのワンピースの下にジャージのズボンをはいている。そんな妙な恰好だから、道で行き交う人は、おや、と一瞬迷うような表情をする。
高校の制服を着た少女たちが顔を見合わせてくすくす笑う。澄子のほうでは、人々の反応など気にしない。彼も今では妻の服装にだいぶ慣れた。今ではどうってことない。
駅から遠いこのツグミ団地の周辺も、宅地開発が進み、公園が整備されている。ひび割れたアスファルトの下から微かに土のにおいが漂ってくる。道のいたるところに生き物の気配が満ちていた。両脇には、小さな町工場や問屋、それに会社の寮なんかが並んでいる。二階のベランダから出勤前の若い男が外を見ながら歯磨きをしている。
住宅地を抜け出て、畑の残るあたりにくると風が横なぐりに吹いてきた。
彼は強い風に当たるとささくれだった気持ちになってしまう。このときも風に頬をなぶられ荒んだ気持ちでずんずんと歩いていった。そうなると、妻のことも何もかも頭から消え去り、気難しい、世界から見捨てられた世捨て人のような気持ちで歩いているのだった。
ふいに、背後から、あああ、とうめき声が聞こえてくる。しまった、忘れていた。慌てて振り向くと、置いてきぼりにされて怒ってるかと思えば、立ち止まって呑気に空など見上げている。
ああぁ。感極まったような声をあげている。空の高みに、ひとすじ、飛行機雲が白い軌跡を西のほうへと伸ばしつつあった。
「さあ、行こう」
彼は妻の肩に手を伸ばして出発をうながす。駅はもう間近だ。時計を見るともう八時半近くだ。この時刻ならもう電車も混んでいないだろう。
奧の空いた座席に澄子をすわらせ、自分は出口のそばで吊革につかまり、ぼんやり窓の外をながめていた。目の前の席の中年女がもじもじと体を動かし、イヤな予感がすると思ったら案の定立ち上がり、席を譲ろうとした。
イヤ、と彼は片手を上げ静止する仕草をした。彼がどうしても座りそうにないとわかると、女は中腰のまま再びすわり、一瞬憎しみを含んだような目で彼を見つめた。人の心は不思議だ。親切心を拒まれると相手を憎むようになるものか。
澄子が自分をどう思っているのか彼には見当がつかなかった。