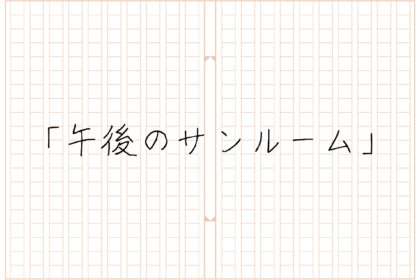ツグミ団地の人々〈立春前 9〉
少し頭を冷やそう。そう思って一階まで降りていくと、すでに人気はなく、受け付けの奧で白衣の人々がゆっくりと動き回っていた。床に高い靴音をたてて横を過ぎ自動ドアの外に出ると家の電話に留守録を入れた。
「少しおそくなります。食事は作ってあるカレーを食べてください」
消え残った雪が植え込みの中で白く浮き上がり、その先にはドラッグストアーの巨大広告塔が今を盛りと光を瞬かせていた。背後に病院の廊下だけが夜のとばりの中にしんと静まり返っていた。
病室に戻ると麻紀さんが、こちらに向かって顔を上げた。
「何時に帰るの。バスの時刻表ならロビーに貼ってあるわよ」
「七時四十分のバスがあるから、それで帰るわね」
麻紀さんはホッとしたような、ちょっとガッカリしたような顔をした。どういう意味なのかは分からないが。
「退院したら、また一緒にコーヒーを飲みに行きましょうね。あ、あなたの家のチューリップのカップでお茶を飲みたいわ」
「もう、もどることはないと思うけど」
「そんなことないって。また元気になって帰れるわよ」
「気休めなんていわなくていいのよ。もう歩けるようになんてならないし、二度ともどれないのはわかってるよ。篠田麻紀の人生はこれでもうお終い……」
麻紀さんは投げ捨てるようにいうと、里子から顔を背けた。そして、窓の外の黒い塊に見える森とその先の何かにじっと目を向けていた。もちろんその先にあるのは私たちの家のあるツグミ団地だ。
「ご主人が、待ってるわ。きっと、一人じゃ寂しいでしょう。
「平気よお」
急に男のように低い声で言った。
「寂しくなんかないわ。あの人喜んでるわ」
「そんなはず、ないでしょう」
「だって、あの女、もう夜中にそっと忍び込む必要なんてないんだもん。きっと昼間からどうどうと来てるに違いないわ」
「麻紀さん、何を言うの」
「あなただって、さっき、聞いたでしょう。薬がキレて動けなくなったあと、アタシがどんな気持ちでベッドでジッとしてたかわかる」
里子は微かに頷いた。
「麻紀さん、あまり考えない方がいいわよ」
「頭の上の方の、ドアの向こうでカチャッと玄関のカギが開いて、あの女が入ってくるのよ」
「気のせいよ」
「いや、違う。あの女はそこで笑うの。ふふって小さい声で。すると夫が言うのよ。しいーって」
「まきさん、誤解よ」
「そんなことないわ。立ち上がってドアを開けて怒鳴ってやりたいんだけど、どうしても身動きできないの。声も出せないのよ。そうして、夫の部屋に入っていくの。全部分かってるのに、動けないの。この気持ちわかる?」