抜け道 (10)
弟はある日、四気筒エンジンのオートバイを人から借りてきて、二人でT川の川っぷちを吹っ飛ばした。少女はよく一緒についてきて、うすい茶がかった目で、弟の走るのをじっと見ていたものだった。
弟は、いきなり土手の横に激しく転倒していた。膝下を四センチばかりも金属にえぐられた。少女は叫び声を上げた。
病院から戻ってくると家の門先に母親が立っていて、彼をひどく叱った。弟はそのころから、女にならだれにでも、母親であれ、女学生であれ、ひどく好かれる質だった。彼はバイクを修理し、借り先に頭を下げに行った。
少女はその日、しまっておいたスカートをはいて現れた。日の丸の旗をもって見送りに出た近所の者たちは顔をしかめたが、少女は平気だった。
彼は心の奥に苦しい嫉妬の棘を感じた。茶色がかって透き通って見える目は懸命に、ゲートルを巻いた弟の姿だけを追いかけていたから。
そのころは駅のある辺りまで畑や雑木林がつづいて、石段を下り森の中の道を弟の後ろにぞろぞろついてきた者たちも、切り通しのあたりではさすがに一人帰り、二人帰りして櫛の歯が欠けるように少なくなった。
それでも少女はついてきた。母親が立ち止まって少女を呼びつけ、もう帰るようにと諭した。
彼が召集されたのは、弟よりずっと後のことで、港から移送される直前に終戦を迎えた。彼は胸の内で弟に大きな負債を抱えた。
弟はすぐには戻らなかった。満州で終戦になり、捕虜となってシベリアに送られていたのだ。弟のいた小隊は壊滅したと聞かされていた。少女は彼の妻になった。
戦後三年たって、憔悴しきった顔で玄関に立ち、すぐに事情を知っても弟は何もいわなかった。町外れに小さなバラックを建てて一人で住み、ブローカーのようなことを始めたが、母親と彼ら夫婦の住む家には滅多に顔を見せなかった。
ある日、弟はぶらりと現れ、縁側に座った。
「そんな他人行儀な・・・・・・座敷へお上がりよ」母親が出てきていったが弟は構わなかった。
ただ荒れた庭だけを見ていた。妻が盆に乗せて茶を運んでくると、ふいに顔をそちらに向けた。
「義姉さん、今年は紫苑が咲かないのかね」
「さあ」
妻は軽く首を傾げた後、弟のほうをまっすぐに見て、
「お母さんに聞いてきます」
そういうなり盆を持って中に入り、弟が帰るまで出てこなかった。
弟は片膝を縁側に立ててぼんやり庭を眺めている。その鉛色の皮膚と沈黙が、彼にある不安をあたえた。
「兄貴よー、人間ってのは、何するかわからねえもんだな。自爆するつもりが捕虜になって、収容所ってのがテントをいくつか張ってるだけの代物で、入れるだけましってもんだった。俺たちは、地面に体一つ入れるだけの穴を掘って野宿生活さ。テントのほうでは、こそこそと俺たちを見ないようにしてた。九月も半ばを過ぎると朝には肝臓のあたりまで冷え切って、テントの奴らの寝首をかいてやろうかと本気で思うほどだったよ」
話が途切れたあとも、弟はだいぶ長いこと庭に顔を向けていた。




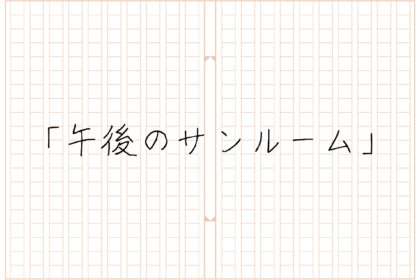






コメントを残す