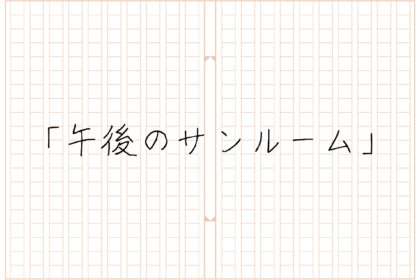ツグミ団地の人々〈二人の散歩 9〉
一時間もせずに彼らはその家をあとにした。
「あの子は、ほんとにバラ作りの名人ね」
後ろから澄子が話しかける。
「そうだな」彼は気がなさそうにつぶやいた。
「あの子が、自分の息子なのが誇らしいわ」
今度は彼も立ち止まって、あとからついてくる妻をしげしげとながめた。
「本当にそう思ってるの」
妻はぴくりとして立ち止まり、ケガをした兎のように首をすくめた。
彼は少々暴力に身を任せたいような粗暴な気持ちになったが、かろうじてそれを抑え、再び歩き出した。妻もそれをなぞるように歩き始める。
彼が前、妻が後ろ。二人はいつも一緒だ。
自分たちはこうやって、いつまで歩いているのだろう。どこまで歩いていくのだろう。いくら考えても彼にはわからなかった。
そのまま家に帰って二人っきりになるのを恐れ、彼らは団地の外れ、海側にあるコーヒーショップつぐみに立ち寄った。
コーヒーショップつぐみは団地の外側をカーブするバス通りにメンしている。坂道を下って行けばびっくりするほど近くに海が見えるのだが、団地の人はだれもわざわざ海を見に行ったりしない。だから、日中ほとんど通りは閑散としている。
店は隆史の中学の時に同級だった娘の母親がやっていた。
「あら、こんな時間に二人おそろいで。めずらしい」
店主の野村美佐子がカウンターの向こうから、愛想良く言った。彼らはアメリカンコーヒーをふたつ頼んだ。
「いつも仲が良いわね。うらやましいわ」
からかうような口調で言った。
「あたしたちが、どこに行ってきたかわかる?」
コーヒーカップを手ではさみ、うまそうに一口飲むと澄子は言った。
「さあ」
美佐子はあいまいに笑った。
「息子に会ってきたのよ」
「あら、隆史君に? 懐かしいわ」
「隆史は今ね、会社をやってるの」
「まあ、すごい」
「かなり手広くやってるの」
おやおや、なんてことを言い出すんだ、と彼は思った。
「素敵ね」
「いつも忙しくて大変そうなの。身体が心配だわ」
澄子は眉をひそめ、ため息をつきながら言った。
妻がここまでデタラメを言えるのに彼は驚いている。それとも、病気のせいなのだろうか。妄想でほんとうと嘘の区別もつかないのだろうか。
「ご活躍でうらやましいわ」
「趣味で薔薇も育ててるのよ」
最後は、付け足しのように言った。
「可奈ちゃんはどうしてるの」
「家を出たきり音沙汰なしよ。隆史君がうらやましいわ。しっかりしていて」
「だいじょうぶよ」
澄子はなぐさめるように言った。彼はあきれて果て、何かいう元気もなく残りのコーヒーを苦い思いですすった。
その時、ドアが開いてひとりの客が入ってきた。