眠り草 (4)
駅には施設の職員が迎えに来るはずだった。空は抜けるような青空である。風もあった。
七十を過ぎた女が立っているには少々寒すぎた。迎えの車は来ない。聡子は一つ目小僧のような一本足の時計の横に佇んでいた。約束の時刻までに二十分ほどもある。所詮、早く来た自分が悪いのだ。
「あなたは、いつも早くきてるでしょう。先にきて待ってる姿がいや」
いつだったか、たった一人の肉親である姉にいわれたことがある。その時はいいがかりのようなことを、と腹立たしく思ったけれど、ひょっとしたら、姉のいうとおりかもしれない。そして本当は、待つのも待たせるのもいやなのだ。
(あたしがいまこんな寒空に立っているのも、そんな性格のせいかもしれない)。自分がとんでもない間違いをしたかもしれない。そう思って聡子はぞっとした。
横にスモックのような制服をきた幼稚園か保育園の子供たちがいて、ひっきりなしに泣いたり叫んだりしている。母親たちは、あーあ、とか、○○ちゃーんと、大声で子供の名を呼んだりしていた。声が空に高く九州されていく。
そして母親も子供たちも、まるで聡子が目に入らないかのようにふるまっている。普段から子供の苦手な聡子はそれだけでこの集団が恐ろしいものに思える。
追いかけっこをしていた男の子が、聡子の腹に激しくぶつかってきた。聡子は転びそうになった。男の子は「ああー」と叫び、母親がこちらに顔を向けた。
そして少し離れたところから叫んだ。
「だいじょうぶ? ぶつかっちゃったわね、けがはなかった」
男の子はうなずいた。
「元気がいいのね。いくつなの」
聡子は微笑みながら聞いた。ほんとは、そんなことはどうでもよかった。
母親は安心したのかふっと笑みをもらし、またどこかに視線を向けた。
自分の子以外は目に入らないようだ。自分が子を産んだことのない聡子には母親の気持ちがわからない。母親になるということは、自分と自分の子以外に関心のないエゴを身につけることなのだろうか。そして、そんな気持ちにならずにすんでよかったと、聡子は思っている。
(自分が、あの子たちを可愛がる気持ちは、何にも代えられない純粋なものだった)。
なぜ自分の育て子に向ける愛が純粋で、母親のわが子に向ける愛がそうではないと感じるのか。聡子はそんな気持ちをおくびにも出さず、微笑みながら親子の集団を見つめていた。





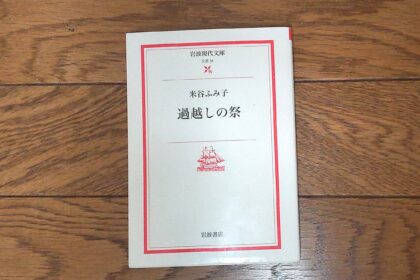



コメントを残す