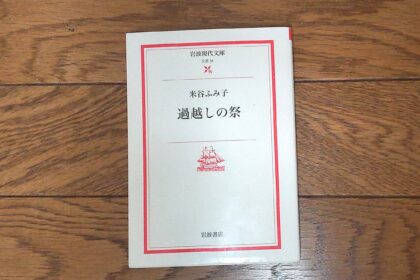ツグミ団地の人々〈二人の散歩14〉
帰ってくると妻は二人分の茶をいれ、また息子の話をする。
「小さいうちからお話しができて、あんなおりこうな子はいなかった。あの子の履いてたベビーシューズを覚えてる? ベルトのところに自動車のアップリケがついてるの。あの子はいつも、指先でそれを取ってしまおうとして、止めると、大きな声で泣きだしてね、ほんとに困ったわ。泣き声が大きいのは、健康な印だっていうけど……」
彼はうなずく。今となっては息子が大きくなったことが良いのか、悪いのかわからない。その時、少し開けたベランダ側の窓から風が吹いてきて、居間の中を通り過ぎていった。彼らもまた風に流され、ここに吹きよせられてきた二枚の葉っぱに過ぎないのだった。
そして今や枯れ葉となって朽ちていこうとしている。それはむしろ恩寵かもしれないのだ。
二人は疲れていたので、テーブルの前の籐の椅子に腰掛けたっきり、しばらく口もきけないでいる。
たがいに、隆史のことを考えているのはわかったが口に出そうとはしない。何年も前には夫婦の間で息子のことばかりが話題になった。けれどもう、そのことについてはひとことも口にしない。
やるべきことをやりつくしたからなのか、それとも忘れたいのかよくわからなかった。
気がつくと部屋の中に澄子がいない。しばらく座って待つが壁の向こうに人のいる気配がない。彼は立ち上がって、ゆっくりドアを開けた。洗面所には旧式の細長い、頭のところと足のところで緩くカーブしたバスタブがある。水の充たされていない、白くて細長いバスタブの中に澄子が横たわっていた。死んだように目を閉じている。彼はしばらくその顔を見下ろしていた。
澄子はふいに目を開けた。そして体を起こすとバスタブの中から這い出してきた。部屋に戻ると妻は声をあげて笑った。
「さっきのあなたの顔ったら」
いつまでも笑い止まない。彼はいささかむっとした。
「心配したんだ」
「ほんとうに?」
「ああ」
「嬉しいわ。あなたと一緒にいた甲斐があったわ」
彼をしみじみと見つめながら澄子は言った。二人の横、洗面所の鏡には妻の嬉しそうな笑い顔が写し出されていた。そして、そんなつもりもなかったのに鏡の中の彼の顔も嬉しそうだった。
ふいに濃いバラの匂いがあたりに充ちてきたようで、彼は脇の下に冷や汗をかいていた。