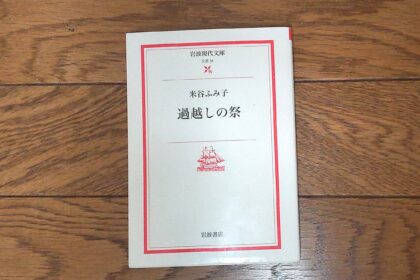「過越しの祭」(米谷ふみ子)。アメリカ人の夫と長男と6年ぶりにニューヨークを訪れる「わたし」が、義姉のシルビアに過越しの祭を共に祝う約束をさせられる
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。
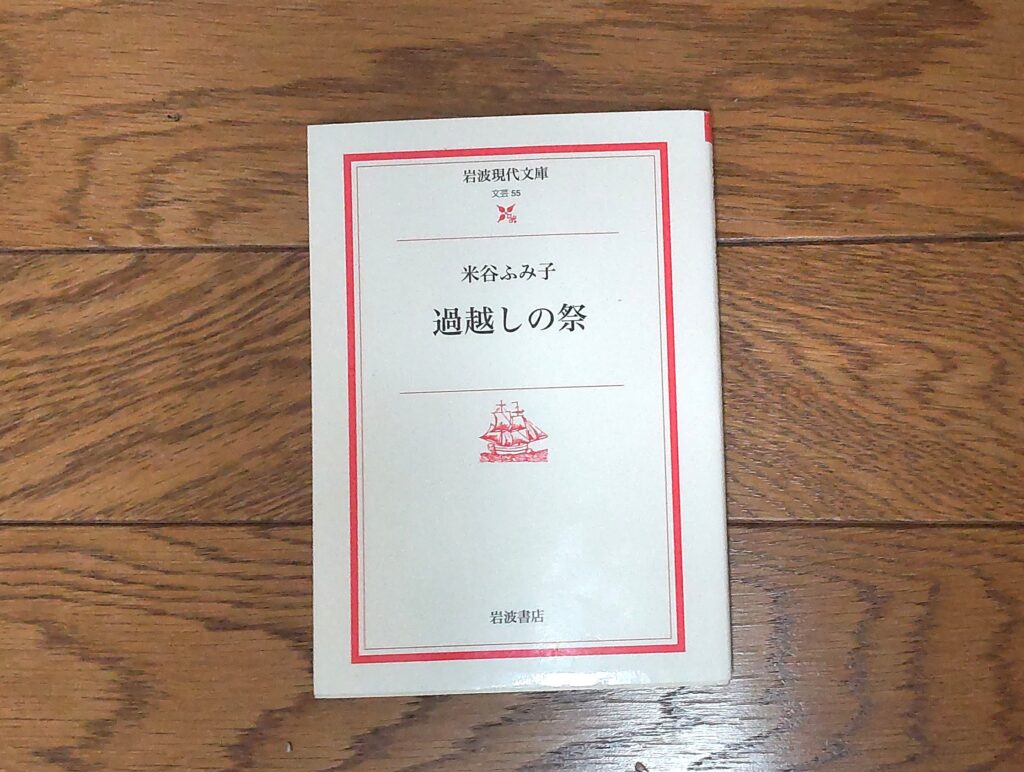
『過越しの祭』(米谷ふみ子 岩波現代文庫)
第94回(1985年)芥川賞作品。ユダヤ系アメリカ人の夫アルと結婚してアメリカに渡った女性(画家・アーティスト)の物語。
ロスに住んでいるが、障害のある次男をあずかってもらい1週間の休暇をとって夫、長男と3人で久しぶりにニューヨークを訪れる。
ニューヨークには気難しくて作者とはまったく合わない義理の姉シルビアがいる。来る早々アルは早速シルビアに電話。そこで、さっそく「過越しの祭」(パス・オーバー・セーダー)のときを、親戚といっしょ過ごす約束をさせられる。
パス・オーバーとは3千年も昔、イスラエルの民がエジプトのファラオから漸く解放されたことを祝う祭りなのだという。
「神がエジプトの初子をあやめた際に、戸口に子羊の血を塗ったユダヤ人の家だけを『過ぎ越した』」という故事に由来しているそうだ。
古代の話はどこかこわいものがある。
「わたし」が気が進まなかったのも多分、義姉のことだけでなく、異教徒の立場で宗教的なまつり(セレモニー)に出席することに臆する気持ちがあったからだろう。夫と妻は、たがいに自由な芸術家としては気が合うのだろうけれど、それぞれの家族さらに宗教というところでは越えられない壁があるようだ。
また、この小説で興味深いのは、当時の自由で開放的なアメリカの雰囲気が伝わってくることだ。けれど底には、叔父、叔母、従兄弟、再従姉妹までつながるユダヤ人の社会が深く根付いている。その中に入るかどうかの瀬戸際の話とみてもたいへん興味深い。
前半には、もうひとつの小説「遠来の客」が入っている。こちらは、障害をもつ次男のことが書かれている。遠雷の客とは、病院から一時帰宅で次男が帰ってくること。肉親の情と、障害をもつ息子を抱えることの困難の間で、引き裂かれる作者の心情が胸に迫ってくる。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。