玉木屋の女房 5
ゆらがこの家にきたのは、お夏が亡くなって半年もたたないころだった。もともとお夏はできた女で、身持ちの悪い清吉にはもったいないくらいの女房だった。
物心つく七つの歳で継母を迎えた多江は、最初のころゆらになじもうとしなかった。義理の母子になったけれど、歳も一回りしか違わない。
「よろしくね。今日から、この家で一緒に暮らさせてもらうよ」
多江は横を向いたまま、顔を上げない。
「きっと、あんたは口をきいてくれないって思ったよ」
「なんて、イヤな女だ」
多江は子供心にも思った。
食事時になっても、すねて部屋の隅で背中を向けていたりしても、ゆらは放っておいた。やさしい言葉をかけるでもない。
一月ほどしてもやはり、多江はゆらに話しかけようとしなかった。
「あたしのこと嫌いなんだろ」
多江は、こくんとうなずいた。
「やっぱりねえ。そうくるだろうと思った」
そして、あはは、と笑った。
不思議に思って顔を上げ、押さえていた指の間からゆらを見ると、大まじめな顔だった。
「嫌いでもいいよ。無理に好きにならなくたって。あんたのお母さんになんて、すぐにはなれないもんね。ちゃんちゃら、おかしいよね。でもね、なんか困ったことがあったらいってよね」
真剣な顔だったので、多江は思わずうなずいてしまい、しまった、と思った。バツが悪くなって、そっぽを向くと、立ち上がり、ばたばたと縁側のほうへ走っていった。
一月ほどたったころ、寺子屋で一緒の絹ちゃんという女の子の家で猫の子が産まれた。近所でも、ネズミを捕るからと、猫も大事にされ、飼っている家も結構結構多かった。ある版元からは、戯画にされた猫が活躍する滑稽本や愛玩の仕方の解説書まで出されるほどだった。
寺子屋の帰りに子猫を見に行った多江は、そのまま一匹をもらって帰ってきた。その家でも何匹も生まれ、持て余していたのだ。
落とさないようにアゴの下にしっかり抱えているのを見ると、ゆらは思わず走り寄った。
「おや、なんて小さいんだろう」
掌に乗るほどの小さな猫が、おゆうの掌の上で震えていた。
「玉や、玉や」
「かってに名前をつけないで」
多江は継母をにらみつけた。
「だってさ、うちは玉木屋だからちょうどいいじゃないか。それになんだか、元気がないねえ」
心配そうに猫の顔をのぞき込み、白魚のように細いしなやかな手で猫のあごから首筋に掛けてするりとなでる。猫は目を閉じたままだ。ゆらの白い手が、それ自体生きもののように動いて猫を撫でている。それが少し薄気味悪かった。
おっかさんになったこの女は、人じゃない。化け物だ。けれど、それほど悪い化け物ではなさそうだった。猫はか細い声でみゃあみゃあと鳴いている。
「おかゆを作って食べさせてあげよう。あんたもお腹が空いただろう。さあ、中へ入って温かいものでも食べようね。ああ、いそがしい、いそがしい」
ゆらはそういってお勝手に駆け込んでいった。




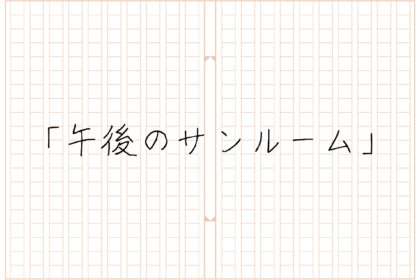





コメントを残す