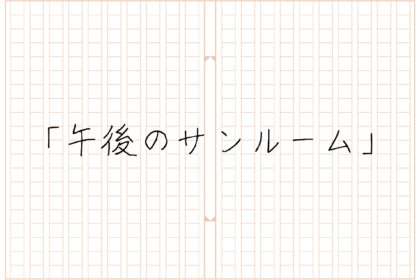ツグミ団地の人々〈立春前3〉
「あ、これ頼まれてたもの」
手さげ袋の中からスーパーのビニール袋に入ったものを取り出す。
「まあ、いいキューリね。うまく漬かったら連絡するわ」
「悪いわね」
麻紀さんはキューリで糠味噌漬けをつくる。ちょうどいい案配になったころ、
「糠漬けを取りにいらっしゃーい」
と電話が入る。
悩みは体が不自由なので野菜をたくさん買いこむと、ショッピングカートを動かしづらくなることだ。
「食事の支度とか、ぜんぶしてるの?」
「そうよ。昨日もミートローフ作ったの。電子レンジでチンすれば、主人が帰ってきてすぐに食べれるでしょう」
「すごい」
「コツは肉をこねるときに、ちょっとマヨネーズを入れること。なめらかな味に仕上がるの」
「マヨネーズを入れるのね」
「おいしいわよ。この前テレビでやってたの。主人が帰ってくるころには、ベッドから動けなくなってるでしょう。だから、そういうものを食べてもらうのね」
部屋の中は雑然としている。床と壁のすき間には埃がたまり、スーパーの袋が床のいたるところに置かれ半分口を開いて中身をのぞかせている。里子は手を伸ばして、さっきからテーブルの下でヒザにもたれかかっている袋のひとつをさり気なく横に押しやった。
麻紀さんは数年前から、筋肉が徐々に動かなくなる病気にかかっている。治る見込みはないそうで一日二度薬を飲んで、効いている二、三時間のうちにすべてをすませるのだ。
ときどき里子の家の窓から、ショッピングカートにぶら下がるようにして帰りを急ぐ麻紀さんを見かける。藤色やピンクの小さい帽子が半分額にずり落ちていて、ああ、薬が切れかけてるんだ、とはらはらする。
夫とは、留学中にヨーロッパの古い街で知り合ったそうだ。大恋愛していっしょに暮らすようになり、日本にもどってから正式に結婚したのだ。顔が輝くときはだいたいそのころの話をしているときだ。
「みんながねえ、主人のこと大好きだったの」
「素敵な人だったのね」
「そうよ」
麻紀さんはいくぶん得意そうだ。その後で、すぐ大きなため息をひとつついた。
「この前も会ってたみたいなの・・・・・・」
顔を曇らすのもだいたい夫の話をするときだ。
「高校生なんて、相手は子供みたいなものでしょう」
「それが、その娘、大人でも敵わないくらい、すごい魅力の持ち主なのよ」
「あなたの勘違いだと思うけど・・・・・・」
「間違いないわ。あたし、あの人のことについては勘が働くのよ。それに、ちゃーんと電話でたしかめたんだから」
また歌うようにいって麻紀さんは婉然と微笑んだ。濃いまつげの奧にあやしい光が瞬いている。紅茶はもうだいぶ冷えかけ、麻紀さんの組んだ腕の前で、食べ残したスポンジケーキの下から半分つぶれたバナナがのぞいている。
「今日は、ほんとに良いお天気・・・・・・」
南向きのベランダからは、惜しげもなく冬の硬い日が差しこんでいる。
帰りに商店街に立ち寄った。花屋の店頭にスミレの鉢が並んで、紫と藤色の花弁を日に向けていた。角の魚屋の店先で若い男の店員が威勢のいい声をかけてくる。
「奥さん、今日はシジミのいいのが入ったよ。買ってかない」
「そうしようかしら」
「これで立春でも過ぎれば、少しずつ暖かくなるんだけどね」
店員はシジミをざっとビニール袋にあけ、くるりと縁を留めて口笛を吹いた。
麻紀さんは南向きのあの部屋で、今ごろはもう薬が切れて動けなくなりじっと天井を見つめているのだろうか。そしてポーチライトの下でマリアは今もイエスの顔に悲しげな視線を注ぎつづけているのだろうか。
そうやって麻紀さんは何年も妄想か真実かわからないものとともに、このツグミ団地の6街区8棟の10階に住み続けていた。
☆ツグミ団地の人々〈立春前1〉
☆ツグミ団地の人々〈立春前2〉