抜け道 (2)
すると彼には、もう何もすることがなかった。
首を巡らすと出窓の上に団扇があるのに気がついた。どうということもなくそれを手に取り、ぱたぱたと数回あおいだ。上半身はランニングシャツ一枚きりなので、暑いというほどのこともない。
キキョウと何かわからない赤い花の浮き出た団扇は、数日前、近くの信用金庫の若い男が置いていったものだ。
その青年は彼の家の玄関に立ったとき、たっぷり汗をかいていた。その上、坂道を上ってきたせいか、上気した赤い顔をしていた。ハンケチで顔をぬぐうと、すぐにたたきに直に置いた黒いカバンから数枚のチラシを抜き出し、腰をかがめて彼に手渡した。
次に白いタオルを出し、最後にごそごそとカバンの横のあたりを探って、ひょいと団扇も取り出すと、それを下駄箱の上に乗せ、
「盆踊りの時にでも、使ってください」もごもごと小さい声でいい添えた。
青年は最近頻繁に彼の家を訪ねてくる。そのたびにタオル、ちり紙、数枚セットのビニール袋などを置いていくのである。タオルや団扇はとっておくが、チラシは面倒なので読まずにその辺に積んでおくうち、大方なくなってしまう。
団扇をもとの場所に戻すと、ぶらりと縁側に出た。生け垣の上のあたりに、どんよりと低い雲がたれこめている。最近、雨の降らない日はいつもこうなのだ。
これから雲の量がふえるのか、それとも薄日が差し始めるのか。今朝は天気予報は聞いていなかった。彼はふいに今日が、ホームヘルパーの遠藤菊子の来る日なのを思い出した。遠藤菊子は今朝の空模様のような女である。
一人暮らしの彼の家にその女が派遣されてくるようになったのは、二か月ほど前からだった。彼は一昨年、喜寿を過ぎたころから膝が痛みだしろくに掃除もしないでいた。
それでも別に困らずに暮らしていたのだが、見かねた隣家の主婦が手続きを勧めてくれて週に二度ヘルパーが来るようになったのだ。
若い女が来るのかと思ったところに、遠藤菊子がやって来たのである。
「けっこうなお住まいですこと」
くすんだ地味ななりをしたその女は、座敷の座布団の上に座るなりいい、彼がいれてやった茶をすすりながら、首をめぐらして家のあちこちをながめ回した。天井の隅にクモの巣がはり、台所の床は黒ずんで、流しの手前にはゴキブリが這っているような、やもめ暮らしである。
そんなものを見ても驚くこともないかわり、いっかな動き出すでもない。実際、家の中をするのが、あまり好きではないのかもしれない。
遠藤菊子は、両掌で湯飲みを包み込むように持ったまま、顔を上げて、古びた茶箪笥の上に置かれた妻の写真に目をとめた。
「奥様ですわね。おきれいですこと」
亡くなったのは十五年前だが、その大分前の写真である。菊子はしげしげと見つめたあと、細いため息をもらし、また茶をすすり込んだ。
「あたしは、もうこんな年ですからね。力仕事は無理ですよ。そのかわり、きれい好きですから、あちこちやらせていただきますわ」
改まった口調でいった。頬なども赤くしているが、六十をいくつか超えているのかもしれない。量の多い黒々とした髪を後ろで妙な形にひっつめている。時間に正確な質だ。ちょうど一時間たつと、そそくさとエプロンを外して帰ってしまう。



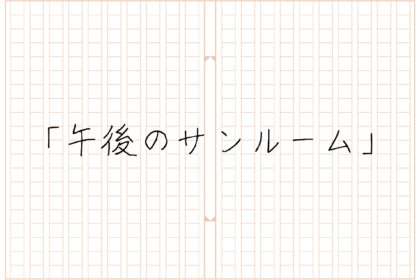





コメントを残す