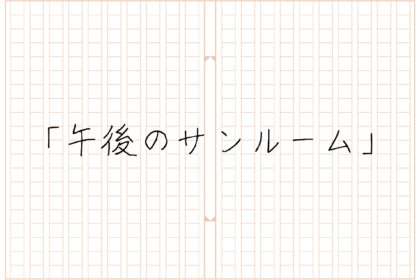グリーンベルト (36)
「ああ、やれやれ、これでやっと日本に帰れるんですね」
恵子さんがあくび混じりの声で言った。
「そうね、なんだかずいぶん長い旅だったような気がするわ」
「それで、ヘレンさんは見えたんでしょうか」
「ヘレン・・・・・・」
何か思い出さないといけないのだが、それが何かわからず私は困っている。頭をふりふり広くもない部屋のなかをうろうろと歩き回っている。
「夕食の支度はだいたいできてますよ」
呆れたように恵子さんが言う。
「鮭は焼いたし、薄切りのお肉はしぐれ煮にしときましたよ。これなら食べやすいでしょう。この前、歯が痛むっておっしゃってたから」
「そうだったわね、この年になると年中どこか痛むのよ」
「お肉は小鉢に盛っておきますか」
「大丈夫よ。自分でやるわ」
「そうですか」
やはりどうしても思い出せない。私は立ったまま、ベランダのほうを見つめている。
ベランダのその先に見える公園を夕暮れの闇がおおい始めている。昼間は、森林公園も子どもが遊んでいたり野球をする子の声が響いて明るいのだが、今はその奥は真っ暗だ。まるで夜の闇を全部ためこんだように
そうだ、あのときのことだ。ふいに思い出した。喉の奥にひっかかっていた小骨が取れたような気持ちである。
「私たちが最後に行ったところを思い出したわ」
帰り支度をすませ、玄関のドアを開けようとしていた恵子さんが突然びくっとして振り向いた。
「ごめんなさい、大きな声を出して驚かせたわね」
振り向いた恵子さんの顔が真っ青だった。
その翌朝、私たちは身支度を整えると下りのエレベーターに乗った。朝は比較的機嫌がいいし、昨夜の諍いのことなどおおかた忘れている。
一階はすでに旅行客たちでいっぱいだった。南米のビジネスマンたちは大きなトランクを床にこすりつけるようにして持ち運び、ビブラートのかかったような声で何かしきりと言い合っている。フロントの女性はまるで詩を書くように勘定書きのうえにペンを走らせている。