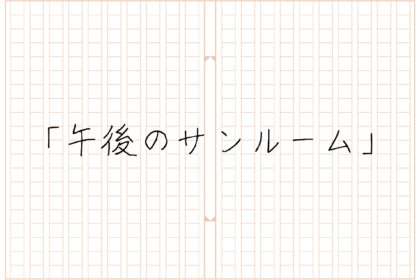ツグミ団地の人々〈立春前 11 了〉
「じゃあ、帰りますね。早く元気になって……」
そういって里子は、寝具の外に出ている細い手を握りしめた。このあと、また会えるだろうか。麻紀さんの夫がベッドの前に妻を隠すように立っている。二人の友情は風前の灯火なのだ。
けっきょく四時間半もいたのだった。その間、何をしていたのだろう。
「転ばないように気をつけてね。今夜、雪が降るそうだから」
麻紀さんがこちらに顔を向けていう。
「そうなのね」
「さっき、テレビの天気予報でいってたのよ」
「じゃあ、また寒くなるわね。風邪をひかないでね」
「まだ、早いんじゃないの。寒い中、バス亭でだいぶ待つようになるわよ」
「だいじょうぶ。ぎりぎりに行って慌てるよりも」
里子は病室からも動けなくなった友人からもその前にボディーガードのように立つ夫からも一刻も早く離れたくなった。
照明の消えたロビーを通り自動ドアから外に出た。
今は巨大な倉庫のように見える病院の建物の横に、駐車場がぽっかりとほら穴のように口を開けている。明かりの消えた商店街のアーケードの外側を楕円をえがくように歩いてバス亭へ向かった。
立春間近の寒い夜だった。ちょうどその時、空から舞い降りてきた細かい雪が頬にあたって溶けていった。
里子はそれ以来一度も麻紀さんに会っていない。
シャッシャッシャッと、ちらしをメールボックスに入れる音ががらんどうのエントランスに響いた。ほの白い明かりの中にちらしが白々と光る。外には闇が濃く広がっていた。麻紀さんが亡くなったと同じ棟の人から聞いたのは、見舞いに行った数週間後のことだった。
ツグミ団地には、実に多くの人が住んでいる。次々といろいろな人が越してきたかと思えば、子育ても済んで夫婦二人だけになった家ではすこしずつ亡くなる人が出てきて、麻紀さんもそんな人のひとりに過ぎない。
というか、本当は特別な友達だったはずなのに里子の頭の中からは、急速にその記憶が薄れ始めていて、多くの団地住民の顔の中に紛れ込んでしまっている。
ふと何かの気配を感じて振り向くと、また例のソフト帽の男の人が立っている。男はわざとらしく新聞を目の前に広げ読んでいるような格好をする。
シャッシャッシャッ。
里子は気にしないようにしてちらしをメールボックスに放り込んでいく。団地に並ぶ建物の外の闇が濃くなっていく。
「変だな。まだ来ない」
男は小さく呟く。
「ここは、3街区の棟で間違いないですよね」
「いいえ、違います、ここは・・・・・・」
振り向いたそのとき、男のほうに近づいてくる女性の姿が見えた。
「あなた、ずいぶん遅かったわねえ」
そばまで来ると女性は言った。歌うような声だった。
里子はハッとした。麻紀さんの声のようだ。とすると、男は麻紀さんの夫なのだろうか。里子が顔を見つめるが薄暗いエントランスの中で、男の顔はソフト帽子の陰になってよく見えない。ただ二人は若々しく、これから劇場やおよばれにでも行くみたいにしゃれのめしているのはたしかだ。
男は女の手を取り、二人は背を伸ばして出口の方に向かった。スーッと自動ドアが開いて白い光がなだれ了込み、あっと立ちすくんでいるうちにドアは閉じ、その向こうにはただ真っ黒な夜の闇が広がっていた。
隣の麻紀さんのいた棟で、初老の男性—麻紀さんの夫が亡くなっていたと聞いたのはその数日後のことだった。
了