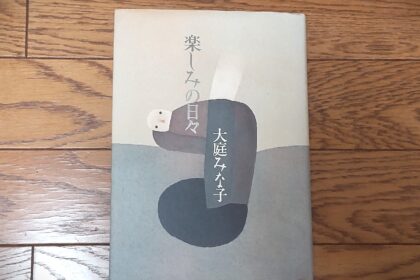ツグミ団地の人々〈苦い水 13〉
尊王攘夷を旗印に挙兵した天狗党は、やがて常陸国筑波山を下ると北へと向かっていった。その間にも武士や郷士、農民らが徐々に加わって人数は千人にも及ぶほどだった。
御城下はもちろん近在の百姓にも尊皇攘夷というのは知れわたっていて、「横浜へ行って、天狗が、港を閉鎖しようとしているらしい」といううわさが立ったが、どうやら横浜ではなく、日光へ権現さまに祈願に出向くらしい、しかも数日後には近くの街道を通過すると聞いて、皆びっくりした。
「てんぐ、てんぐ」と子供たちが呼ばわるたび、親たちはあわてて子供の口をおさえて家へ連れ帰ったそうだ。いや、その行列のすごいこと。町の者や百姓らは道の横に這いつくばり、頭を垂れて行列を見送った。
先頭に、斉昭公きたえの鎧どおしを乗せた神輿がしずしずと進み、おおぜいの白装束の男たちがそれを引いていた。お侍がたは陣羽織に袴をはいて馬にまたがり、鉄砲や槍をもった男たちがあとについて歩いていた。そういった下賎な者たちでさえ、ふだんそこいらで見かける顔とはちがって神々しくさえ見えた。引いていた自在砲には、「発而皆中節」の五文字が彫られていたが、「打った者には百発百中お返ししてやるぞ」という物騒なものだった。
その日、見に行ったのはひい爺さんばかりではない。村の主だった者はみな見に行った。けれどついて行ってしまったのは、ひい爺さん一人だった。まだ二十代半ばの血気盛んだったひい爺さんが、鍬やくわを畑の真ん中に放り出して故郷を出奔したのは、その翌日のことだった。
日光から筑波に戻る道すがら、天狗はますますふくれあがった。天狗の名を語り金を脅し取る者もいたから、天狗を恐ろしいもののように思い、決して口の端に乗せない者もいた。ひい爺さんも鍬を持つかわりに、手に鉄砲か槍を持って、行列の後ろについて歩いていたはずだ。土地に根付いている百姓がそんなに何百キロもの移動をすることになるなんて、ほんとに不思議なことじゃないか。
移動を始めてすぐにひいじいさんは、隊をはなれることを考えた。けれど歩き出すとすぐにそんな考えは消えてしまった。集団はひとつの意志をもつ。運動の法則によって、動き出したものを留めるにはその何倍ものエネルギーがいる。 集団は核心部から離れるに従って、烏合の衆と化すはずだが、そうはならなかった。厳しい戒律が課されていて、まわりの村に危害を加えたものは切腹、という厳しいオキテがあったのだそうだ。
そしてやがて、水戸様のいるご城下近くまでもどってきた。そこには、避けられない決戦が待っていたのだ。