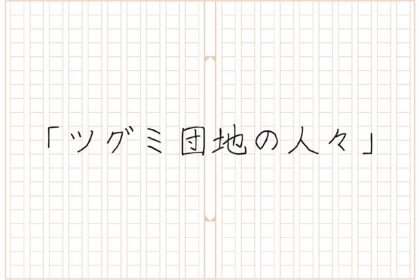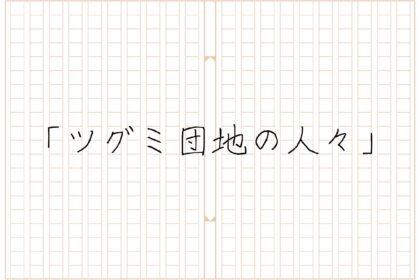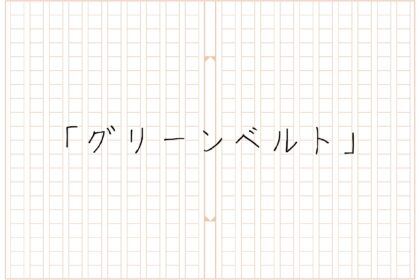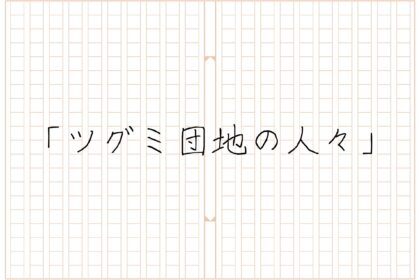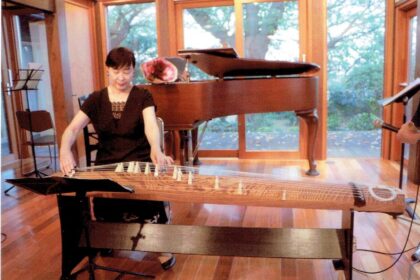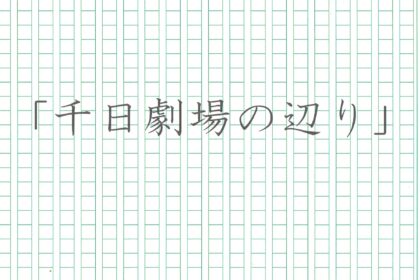玉木屋の女房〈18〉
食い詰めたら親子三人、江戸を離れて田舎にでも行こうと、言うが、とんでもない、江戸ものはだから困るとゆらは思う。
おゆらの頭の中には故郷の上州での飢饉の際に見た悲惨な光景が浮かんでくる。江戸もんの夫には想像もつかないだろう。
その年、夏のさかりにも日の照る日は少なくて、稲穂には実が入らず、秋になる前から農作物は壊滅的な被害を受け、農村では娘をいよいようらなければなんめえ、とおっとうが、頬にあかぎれを作った娘の顔をじっと見つめるのだった。
なに、まようこたあねえ、肩入れ屋では、少なくても、飯はたっぷり食べれるだろうよ。そんな風に、腹を空かして、人様のにぎりめしをじっと見つめる、なんてこともなくなるんだ。
口入れ屋の五平は、わざわざ人様が一番腹の減る日暮れ頃をねらってやってきては、縁側に座って、旨そうににぎりめしを食べるのさ。そばにいる娘が、死にそうに腹が減って食い入るような目でにぎりめしを見つめてるのをちゃんと知ってるのさ。飢饉は人を人にはあらず、餓鬼にするのだ。
それが故郷を思い出すたび、ゆらの頭の中に浮かんでくる光景だ。それに比べたら、吉原での暮らしはどれだけ楽なものだったか知れない。少なくてもおまんまにありつけない、ってことはなかったから。
頬がこけガリガリにやせて、目ばかり大きな子どもを女郎たちは不憫がり、残り物の飯やもらいものの菓子などを暇を見つけては、ゆらの手ににぎらせてくれるのだった。
やがてまともに食べられるようになると、ほおはふっくらとし、赤みをおび、その年頃の少女らしい可愛らしさがあり禿となって花魁道中などにもついて歩き、やがて新造となって際だった美貌とは言えないがそれなりにみんなに可愛がられた。
そして清吉からの落籍話が出たときには、松葉屋の主はもうけ主義と言うよりも、どちらかと言えば、ほどほどのところで気質の生活に戻してやろうという温情めいたものだった。