眠り草 (3)
どうしても送っていくという健治をふりきって、聡子は日曜日の早朝に家を出た。健治はもちろん、美咲もまだ眠っている時間だった。
「明日は何時に出発するの。見送るよ」
「わたしも」
この家で過ごす最後の夕食の席で、兄妹はいったが、
「結構早い時間だから大丈夫よ、見送らなくていいわ」
湿っぽい別れの場面などまっぴらだった。いや、よく考えれば自分がこの子たちと別れるのを認めたくないのかもしれない。
聡子はキッチンからよく焼けたチーズグラタンをテーブルに運びながらいった。この兄妹の小さい頃の好物で聡子はそれを何回作ったかわからないくらいだ。テーブルの上に乗せるとジュルジュルと弾ける音をさせる。それは幸福の音だった。
「うわぁ、おいしそう」
美咲はいった。美咲は二八歳になるが、この時期特有の不安定さで、
「あたしは一生結婚しない」といったり、「だれかいい人いないかな」などといってみたりした。
美咲がこの家を離れるのは当分無理だろう。
そう聡子は思っている。気持ちが不安定なのだ。それは聡子がこの娘を大事に育てすぎたせいでもある。母親以上に甘えさせ、なんでも聞きいれる。
きっと母親ならば、もっと厳しくしつけもしたのだろうが、聡子はただ甘やかした。それがつまり血のつながりがないということなのだ。
「二人も他人の子を育て、自分は結婚もせずに今まで」
「ご自分を犠牲にしてねえ」
など他人がおだてるが、心からそう思っているのでないことは明らかだ。聡子の健治と美咲に対する愛は慈愛とか、犠牲とかそういうものとは、ほど遠い。二人の子を育てるのは、まるで甘い蜜を飲み干すような甘美な事柄だった。
そして思う。好きなだけ愛するというのはなんて放縦なことなのだろうと。けれど、それももう終わりだ。明日、自分はこのなじんだ家を出て行く。洋一は、二人の子を育ててくれた聡子に報いるために十分な〝退職金〟を用意し、さらに聡子の希望をきき、彼女の意に沿った住まいも見つけてくれた。
「ずっと、この家にいたらどうですか」
洋一はそういったが、本心でそう思っているのでないことは明らかだった。
それに彼ももう若くはない。そろそろ、会社を健治に任せ自分は引退したいと思っている。あと継ぎの健治のために結婚相手も見つけなければならないだろう。この家に同居するにしろ、しないにしろ聡子の複雑な立場が、結婚相手を困惑させるに違いなかった。
聡子にしてからが、もうこの家に自分が必要とされていないのを知っている。食事の支度やそうじなども変わらずつづけているが、それはもはや、誰にでもできることだった。それに二人の兄妹が、坊ちゃん育ち、お嬢さん育ちでどこか頼りないのも、ひょっとしたら自分がいるせいかもしれなかった。
聡子は朝早く家をでた。門扉を開けて外に出ると早朝頼んでおいたタクシーが外に待っていた。
門扉を再び閉めてふりかえる。庭に続き、。沢田家のレンガの壁のいかめしい家が見える。二階の窓を見ると健治がこちらを見ている。どんな表情なのか、年を取って視力の弱った聡子にはよくわからない。
「気をつけて」
といったようにも思えるが、それは朝、子どもたちを送り出すとき聡子がよく口にしていた言葉だった。涙ぐみそうになり聡子は慌てて車に乗り込んだ。






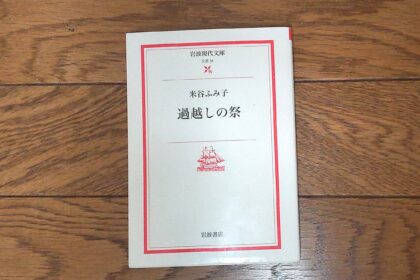



コメントを残す