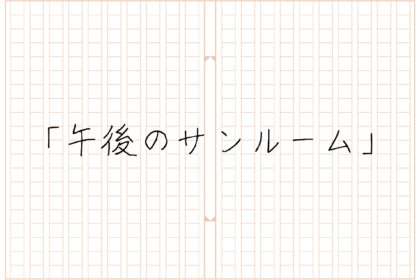ツグミ団地の人々〈レモンパイレディ 10〉
「やさしい子でね。ほんとうは会社で働けるような子じゃなかった。前の日に就職斡旋会社に行って登録してきたのよ。がんばって必ず探してあげると、窓口にいたお姉さんはいってくれたらしいの。思ってたより感じよかった、とうれしそうにいっていたのに。
その日は朝8時に起きてきたの。だから大きなオムレツを作ってあげたの。あの子が大好きだったのよ。それとトースト、ミルクをたっぷり入れて紅茶を飲み、一緒にテレビでアメリカのロボットの出てくる映画を見たわ。
いえ、ロボットじゃなくて、人間がロボットになってしまう話だったわ。死んでもう人間として生きていくのが不可能で、マスクの下の顔以外はぜんぶロボットになってしまう、そんな刑事の話だった。そのロボットは、いえ、人間っていうのかしら正義感に燃えていてとても強いの。それなのにロボットの頭の下には、とても青白い死人のような顔があって、それを見るたび娘は悲しそうな顔をしたわ」
あ、ロボコップだって思ったけれど口には出さなかった。
「娘はそれを見終えると黙って部屋にいって、夕食まで、ちょっと出かけてくるよ、と言ったわ。1日に1回は外に出たほうがいいから。そりゃ、そうよ、とわたしは笑って送り出したけれど、夕食の時間が過ぎても夜中になってもあの娘は帰ってこなかった。・・・きっと一晩中、プールの底にいて、星を見ていたのね」
「ベランダからプールが見えるかと、伸び上がって見るんだけど、ちょうどお宅の家の居間がせり出していて見えないの」
岡田さんはちょっと悲しそうに言った。
「ね、なんてかわいいんでしょう。寝顔を見てやってくれる?」
シミの浮き出た手でふとんをそっと持ち上げると、硬質の白いすべすべした肌が現れて、市松人形のような真っ白い人形の顔がひっそりと天井を向いていた。小さな赤い唇がちょっと開いて笑っているように見えた。
「ぼっちゃん、ちょうどあんたの立っている背中の向こうに学校のプールがあるでしょう。そのプールの底に、あの子は横になってたのよ。まるで日光浴でもしているように斜めに横になってたのよ。まるで日光浴でもしてるみたいに。早く出ておいで、って叫んだけど、あの娘は動かなかった」
僕は下を向いてじっとしていた。少しして、おばさんは、ハッとしたように僕の方を振り向いた。
「ああ、そうだった。坊ちゃん、すっかり待たせちゃったわね。もう、おうちへ帰らないと」
岡田さんは、部屋のサッシを開けるとベランダに出て僕を手招きした。
「さあ、こっちよ」
僕んちのベランダと岡田さんの家のベランダは避難用の高い板で仕切られている。
「ここをまたいでいけば、あんたおうちに帰れるでしょう」
「はい」
おばさんが置いてくれた台の上に乗り、そこから仕切り板に足をかけた。
おばさんの手が僕の背中を押してくれる。まさか、落とされるのでは、とハラハラしながらよじ登った。下を見れば公園の隅にまたあの酸素バッグがゆらゆら揺れている。脚がガクガク震えていたけれど、ようやく板のてっぺんをまたいで、反対側の僕んちのベランダの上に着地した。
おばさんが板の向こうから大きな声で言った。
「まあ、無事に降りられてよかった。ホッとしたわよ。また遊びにおいでね。坊ちゃん、あんたなら、あの娘のいい友達になれるわ。きっとよ。あの娘も喜ぶわよ」
僕はもう夢中で、サッシを開けて自分ちの室内に入っていった。