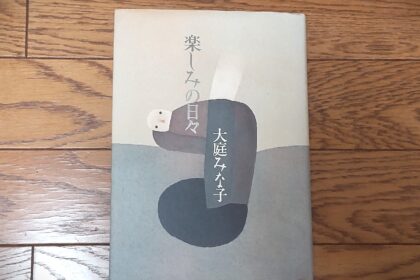ツグミ団地の人々 〈レモンパイレディ2 〉
第一次世界大戦のおり、アメリカ軍がどこかの国に派兵されていた。従軍記者が国に帰るときに、一人の兵が記者に十ドル紙幣をにぎらせていった。
「これをレモンパイ・レディにわたしてくれないか。戦争について不平をいう女がいたら、思い切りレモンパイを投げつけてやってくれ、って」
当時アメリカのいろいろな町のパン屋に、レモンパイ・レディというのが出没したそうだ。パン屋の店先である女が、
「くだらない戦争のせいで、生活が苦しくなった」
そうもらすと、店にいた客の女が売り物のレモンパイをつかみ、不平を言った女の顔に投げつけたというのだ。
想像するにこの女はきっと、髪がくるくる派手にカールして、顔にはたくさんのシワがよっているにちがいない。そして一度も笑ったことがないような顔をしている。だれのまわりにも1人はいるそんな女だ。
思い出したのは、ツグミ団地にいたころの、ある日の夕暮れ過ぎの光景だった。僕の家では夕食の準備が整うと、それぞれが勝手なことをしていた家族が自然に居間の横にあるダイニングに集まってくる。僕はなんだかうれしくて部屋の隅で笑い続けている。
「わけもなく笑うんじゃありません」
母さん、がけっこう厳しくいう。「だってさ・・・・・・」
そういって僕はまた笑う。顔がゆがんで、だんだん苦しくなってくる。
みんながそれぞれ自分の席につく。まわりは少し暗くして、食卓の上のペンダントだけが家族の頭の上にぼんやりと淡い光を注いでいる。食事のときに幸福という名の一幅の絵のように見えることを母は好んだ。
そのとき、斜め向こうの隣のベランダから、ちぢれた頭がのぞく。その下の目がじっとこちらに注がれている。燃えるようにキツイ目だ。ちょうど少し前、西に沈んでいった夕日の残光が目の中に飛び込んできたように。
「さあ、もう食事はおしまいよ」
いきなり母親が叫んで立ち上がる。こんな風にして今日の団らんは終わる。
僕ら一家がツグミ団地に越してきたのは、もう二十年も前のことだ。僕はその時七歳だった。
そもそもは、父が新聞の折り込み広告のチラシをなんの気もなく手に取ったのが始まりだった。部屋の間取り図をつぶさに見ながら父はつぶやいた。
「築十五年はたっている。それでも上等だよ、俺たちの家には」
休日に僕らは父のベージュ色のカローラに乗って、区の東端にあるその団地に出向いていった。国道をしばらく行くと、遠くの森の向こうにばらばらの高さの建物群が空に向かって屹立しているのが見え始めた。
「ああ、あそこなのね」
母さんがため息をつくようにいった。
車は何度か右に左に曲がりやがて僕らは迷路のような、団地の道の片側に車を停めた。完全に方向を見失っていた。
父さんは車をおりてだれか人が通らないかとあたりを見回した。けれど生憎だれも通らなかった。
「なぜだれもいないんだろう」
道路のそばの茂みは徐々に深くなっていって、その奥に何本かのかなり大きな木がそびえている。「あ、奥に公園のようなものが見える」
母は雑草の間を抜けると、ずんずんと林の中に入っていった。
やがて水色のカーディガンを着た母の背中は木の緑と白っちゃけた木肌の奥に見えなくなり、まるで木々が母さんをすっぽり呑み込んでしまったようだ。
父さんが母さんの行く先を目で追ったが、声はかけなかった。道路をはくように風が黄色の砂煙を舞い上げて通っていった。父は車の車体にもたれながら煙草に火をつけ、近くの棟を見上げた。
「なかなか、いい団地じゃないか。ここなら気持ちよく暮らせそうだな」
遠くで干した布団をたたく音がやけにおおきく聞こえる。
見上げると、いくつもの高い棟のベランダにはどこもびっしりと布団が干され、風で洗濯物がはためいていた。その中の家のひとつになるってことが途方もないことのように思えた。僕らはまだ、ここの住民の一人にもお目に掛かっていない。
土曜の昼下がり、外を歩く人の姿はまったく見えない。向こうから人が歩いてきたら、それが本やテレビでよく見る例の宇宙人の姿何じゃないか、とそんなことまで想像させる無人の街なのだった。
しばらくして母さんはもどってきた。顔色が背後の森のようにやや青みを帯びて見える。
「驚いたわ。学校のような建物があるの。でも校舎にも、校庭にもだれもいないのよ」
「今日は土曜日だからだろう」
「そうかしら。それにしてもひっそりとしてまるで人の気配が感じられないの。気味が悪いわ」
「さあ、もう行こう。夕方になってしまうよ。とにかく人を探して道をきかないとな」
母さんはそれから気持ちが悪くなったといって少し休んだ。