玉木屋の女房 〈13〉
蔦屋重三郎の思惑どおり、写楽という絵師の絵は大評判になった。江戸っ子は目新しい物好きだ。これまでの浮世絵といったら、北尾重政の「青楼美人合姿鏡」、喜多川歌麿の「江戸三美人 富本豊雛、難波屋おきた、高島おひさ」などのような、美しくなよやかで、あだっぽい女の絵が主流だった。
そんな中で、写楽の絵の人物たちは美しくも、あだっぽくもなく、むしろゲテモノ、キワモノの類に見えたしある役者の絵などはまるで人生を馬鹿にしくさっているようにも見えた。
中でも度肝を抜いたのは、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」だった。誇張された表情や、赤く縁取られた目、一文字に惹いた口などあまりに生々しく、極端すぎた。前に突き出された両手はまるで赤子の手のように小さく気味悪かった。
「悪役には違いねえがな、これだけ悪そうな格好にしなくても」
「やれやれ、あの役者も気の毒にな。まるで違った姿に描かれるなんて思いもしなかっただろうよ」
人々はそんな風に噂し合い、まだ見ぬ者はその噂を聞きつけて一目だけでもその絵を見たいものだと思った。流行に遅れては話にならないのだ。
耕書堂の店の者たちでさえ気味悪がったのに、なぜか、あれよあれよという間に江戸中の評判になった。絵師が無名だったことも、流行に拍車をかけますます人々の興味を惹き、毎日店の前には刷り上がった絵を求める人々の行列ができていた。たまに着流しのような格好で現われて、そんな様子をちらりと見ては、呆れたような様子で立ち去っていく役者風の男がいたが、それが東洲斎写楽その人だと気づく者はいなかった。
彼はただ自分の知っている役者たちの絵を姿をなぞるように描いていたつもりが、いつしか役へのこだわりや、不運、人の心の裏側のおぞましさなどを生々しく描き出すことになってしまった。
そこに、人々は共感し、ヤンヤの喝采を浴びせた。いつしか彼はもう自分が二度と役者には戻れないのではないかという不安を感じた。仮の姿でしかない写楽がいつしか本物の彼を乗っ取っていた。

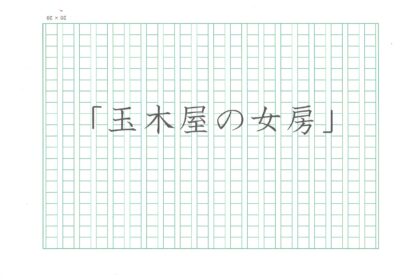
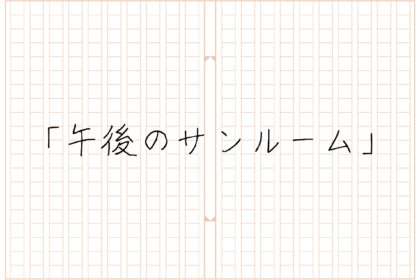
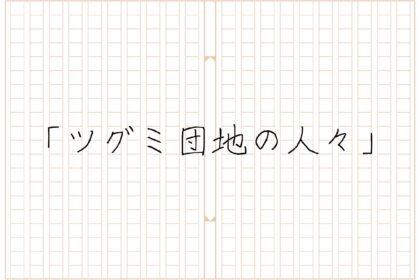
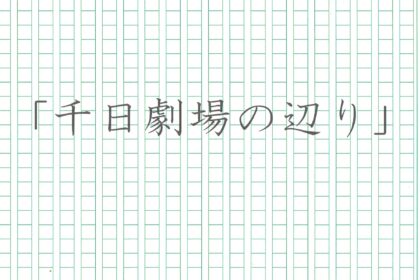
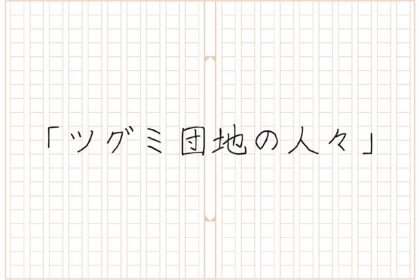

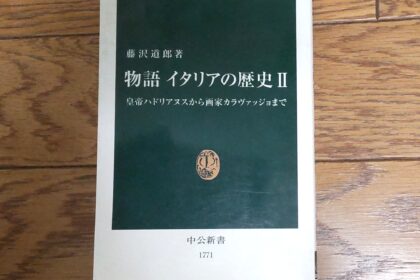



コメントを残す