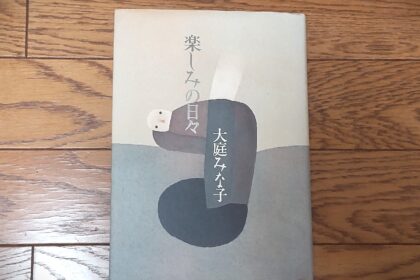ツグミ団地の人々〈二人の散歩2〉
夢の中で彼はあの男になりきっていた。
「この茶碗はいいだろう」
古い通路を抜けて、暗い展示ケースの前に立つと彼は得意げにいった。そうして振り向くと妻がいない。った。
「しまった、どこに置いてきたのだろう」
背中をスーッと寒気が走った。そして目が覚めた。
いつ頃からか、彼は朝目覚めてすぐにベランダに出るようになった。いっときでも一人になりたい、自分の心の奥を探れば、そんな欲望があるのかもしれない。
「馬鹿な……」
彼は首をふってその考えを打ち消した。
ベランダの手すりの向こうに、大輪のバラが一輪だけ咲いている。人間の目のように首を傾け、まるでこちらを観察しているようだ。
「なぜあたしを見るの」と、まるでそう言っているような。
後ろで、サンダルをつっかける音がする。彼は振り向かない。妻が息を切らしながら近づいてくる。
「あなた、あなたったら、なぜ返事しないの」
「そうだな」
彼はゆっくりと振り向いた。やせて、むくんだ顔をした妻の姿があった。青白い眉間に癇性なシワを寄らせている。
「まあ、笑ってる。朝から、何がそんなおもしろいの」
「なんでもないさ。さあ、中に入って朝食にしよう。ロールパンと食パンがある。どっちがいいかな。それからベーコンエッグと……」
「あたし、レタスをちぎってサラダを作るわ」
「頼むよ。味つけは、オリーブオイルと塩だけがいいな」
「わかった。オリーブオイルと塩だけにするわ」
部屋に入る前に一度、手すりの下をちらりと見る。バラは黒ずみ、もの問いたげに彼を見ている。彼を見とがめるように妻は言った。
「さっきは、あんなに前屈みになって。ベランダから落ちるかと思った」
「そうか。バラを見てたんだ」
「六階から落ちたら命がないわ。あんたは、いつもあたしに心配ばかりかけるのね」
「それは、それは、すみませんでした」
しばらくすると気が済んだのか、澄子はけろりとした顔でキッチンへ向かい、彼もその後をついていった。
妻は冷蔵庫の野菜室からレタスを取り出して洗い始める。ベーコンエッグは彼の役目だ。
澄子はすぐに、火を使っていることを忘れ、ゴミ出しや洗濯など他の用事を思い出しキッチンを離れてしまうので、危なっかしくて仕方がない。かと言って彼が作れるメニューときたら、半熟卵にベーコンエッグだけなのだが、二人とも決して飽きたとは言わない。
焼き上がりを皿に乗せ、サラダボールに入ったサラダと、トースト、熱い紅茶があれば、二人だけの朝食になんの不足もない。
レタスを口に入れると、酢の味が口の中に広がり酸味の苦手な彼は思わず顔をしかめる。あんなに言ったのに・・・・・・、忘れてしまったんだ。
「酢を入れただろう」思わず強い口調になる。
「入れてないわよ」
妻がムッとして返事をする。
「あたしを信用しないのね。あんたは、いつもそう」
このまま放っておくと、どこまでもエスカレートする。いい加減なところで切り上げようと、彼は話題を変えた。
「今日は病院だったな。そのあと、気晴らしにどこか回ろう」
月に一度、妻を数駅先にある総合病院につれて行っている。
妻が買い物に出て道がわからなくなり、近所の奧さんに家に連れ帰ってもらったのが二年前のことだ。それ以来、少しずつ少しずつ進行しているのだ。
病院は、彼ら夫婦がかつて住んでいたアパートの近くだ。
かつては畑なども点在する静かな住宅地だったが十数年前、都心から大型デパートが進出し、駅ビルや立体交差の下を大勢の人や車が行き来する繁華街になった。
「久しぶりに、歩いてみたいわ」
「俺はもう年だから、人の多いのは苦手なんだ」
彼は先月七十歳になった。内心まだまだと思っているが天の邪鬼だから、わざと年寄りくさい口ぶりをするのだ。
「家にくすぶってばかりじゃ、くさくさする」
「家が一番さ」
彼は同意を求めるように、ふとだれもいない窓の外に目を向けた。