もし承久の変がなかったら「京都×鎌倉 大蹴鞠カップ」が開催されていたかもしれない。中心選手はもちろん後鳥羽上皇と時房。
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。
ワールドカップで盛り上がっているサッカーですが、発祥は中世イングランドとも言われ、もともとフットボールという名称でした。
少し前の「鎌倉殿の13人」を見ていたら、ひょっとして、発祥は日本の中世の「蹴鞠」ではないかと思ってしまいました。それほど、後鳥羽上皇と北条時房のボールさばきならぬ、鞠さばきは見事でした。

後白河法皇も個性的な方でしたが、それに負けないくらい後鳥羽上皇もいろいろとユニークなエピソードをお持ちのようです。というか、これほどに多才で、劇的な生涯を送られた方は歴代の天皇の中にもそうそうおられないのでは・・・。
安徳天皇のあとを受け1183年に4歳で即位し、19歳で譲位。その後は院政をしいて政治を行いました。歌人としても秀でていて、藤原定家らに「新古今集」を編さんさせました。
源実朝とも和歌で交流を深めましたし、「方丈記」の作者鴨長明の和歌の才を認め、さらには神社の神職まで見つけてあげようと骨折りました。人情派の上皇様でもあるのです。
琵琶の演奏も名人級、なんと刀剣もご自分で焼きをいれたそうですから、かなりの凝り性です。
このように多方面に才能を発揮されましたが、神器なき即位だったことがずっと負い目になっていました。三種の神器は平家が持ち去っていて、特に草薙剣は海に沈んだあと、いくら探しても見つからなかったのです。
先々週の「鎌倉殿の13人」の中ではそんな後鳥羽上皇が、北条時房と楽しげに鞠を蹴り合い、リフティング? までする場面が描かれました。ここ圧巻でしたね。負けず嫌いのお二人の顔は、すでにスポーツマンのものでした。
このようになんでもお出来になる後鳥羽上皇が承久の変の後、隠岐に流され、その地で崩御されたのは悲しいことです。もし宮中にいらしたら、ワールドカップならぬ、「京都×鎌倉 大蹴鞠カップ」なるものを開いてくださったかもしれませんね。
京都と鎌倉の文化がさらに花開いたのではないかと残念に思います。
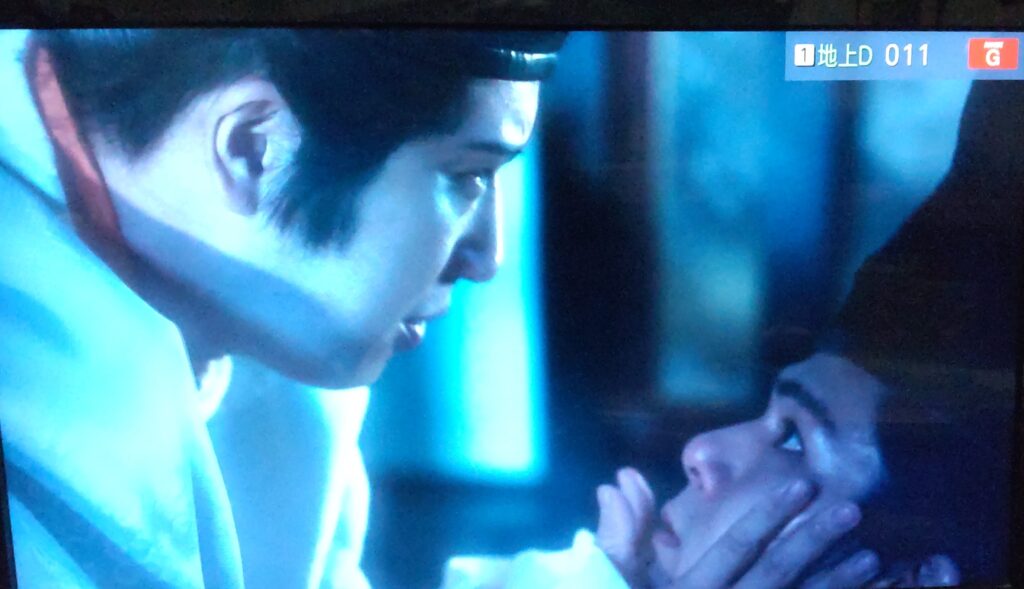
尾上松也さんが才能あふれる後鳥羽院の雰囲気や、いかにも勝ち気そうな様子を大変魅力的に演じてらしていつも楽しく拝見しています。これから後の運命を思えば少し悲しくもなりますが・・・。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。









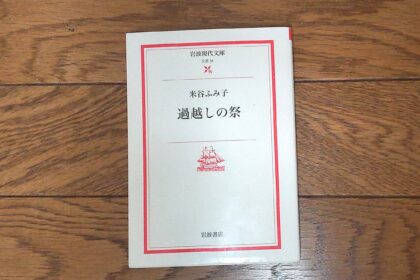

コメントを残す