漱石の「夢十夜」は、人の意識の底の恐怖やあてどもなさ感じさせてくれる。
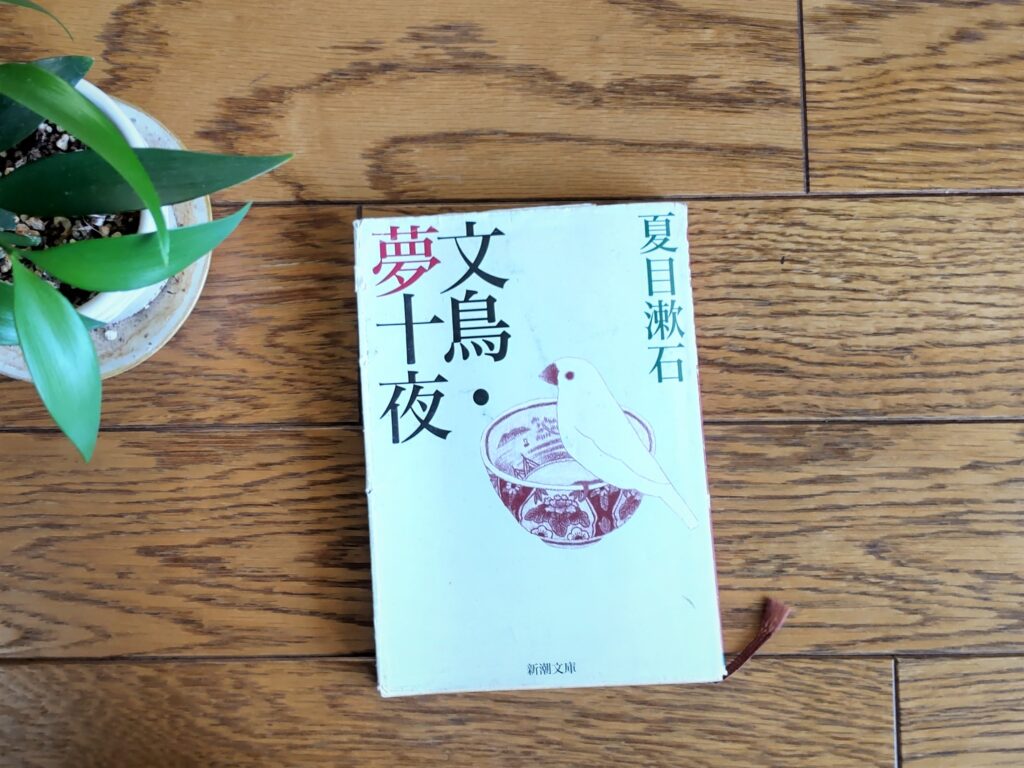
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。
「夢十夜」を読んでいると頭の奥がくらくらしてくる。そして、そのくらくらの中に浸っていいんだよ、といわれているような不思議な作品。
漱石はどういう気持ちでこれを書いているのか。まるで精神分析家のように、ちょっと斜めから意地悪な目でながめてみたくなる。いったいどうしたのですか、漱石先生と。
しかし、漱石ほどの作家が、そう簡単に創作時の心などシロウトに見せるはずがない、これは川端康成の「眠れる美女」のように、心を解き放しつつ技巧で武装しているそんな小説なのだろう。とりあえず、この夢の中に気軽に入ってみればよい、と漱石が言っている。だから肩肘張らず夢の十夜を味わってみよう。
「夢十夜」は題名の通り十の夢からなっている。すべて夢の中の世界なのだが、夢という言葉から連想されるようなロマンチックな内容ではない。夢の中には隠れた願望が表れてくると言う。漱石もその夢の掟に従い自分の恥ずかしい願望や恐れ、原始的恐怖を解き放って書いている。設定はそれぞれ別なのだが、途方もなさや恐れ、夢の中で凍り付くその瞬間を怖いくらいに的確に表現している。
すべて話は、「こんな夢を見た」で始まる。
もっとも印象に残るのは第一夜、「私はもう死にます」という女の話。死んだら埋めてくれ、そして離れずに100年待っていてくれ、という。日が西から昇り東に沈む。やがて男は100年たったのを知る。すると地面から・・・・・・と、こういう話。こわいですねえ!
そしてもっとも恐怖なのが、第三夜の六つの子供を背負っている話。背中の子はいつのまにか「青坊主」になっている。そして背中からあれこれと偉そうに指図する。「自分は我が子ながら少し怖くなった」。そして杉の根の所までいくと、背中の子はいきなりとんでもないことを言い出す。それはまさしく背中が凍えるようなことだ。このゾッとする瞬間はまさしく私たちが夢の中で奈落につき落とされるあの感覚なのだ。
夢の中で探しものをし、することを忘れ、わけもわからない恐怖の中に落とし込まれていく。それはなぜなんだろう。夢の中の世界を再現するようなこの話を読めば少しは夢の中の恐怖の正体に近づけるかも知れない。夢十夜はそんな世界を描いている。昼間の飾りをはぎ取られた人間の心は小鳥のように繊細でか細いのだ。
最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。





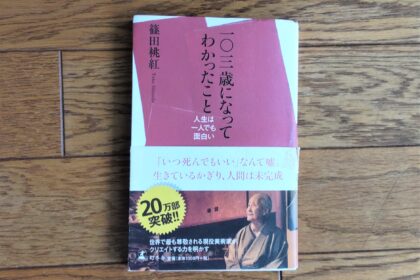
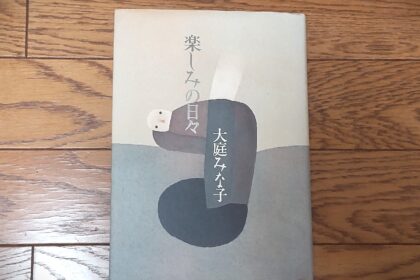




コメントを残す