千日劇場の辺り ―奇妙な案内人
千日劇場の辺り ―奇妙な案内人
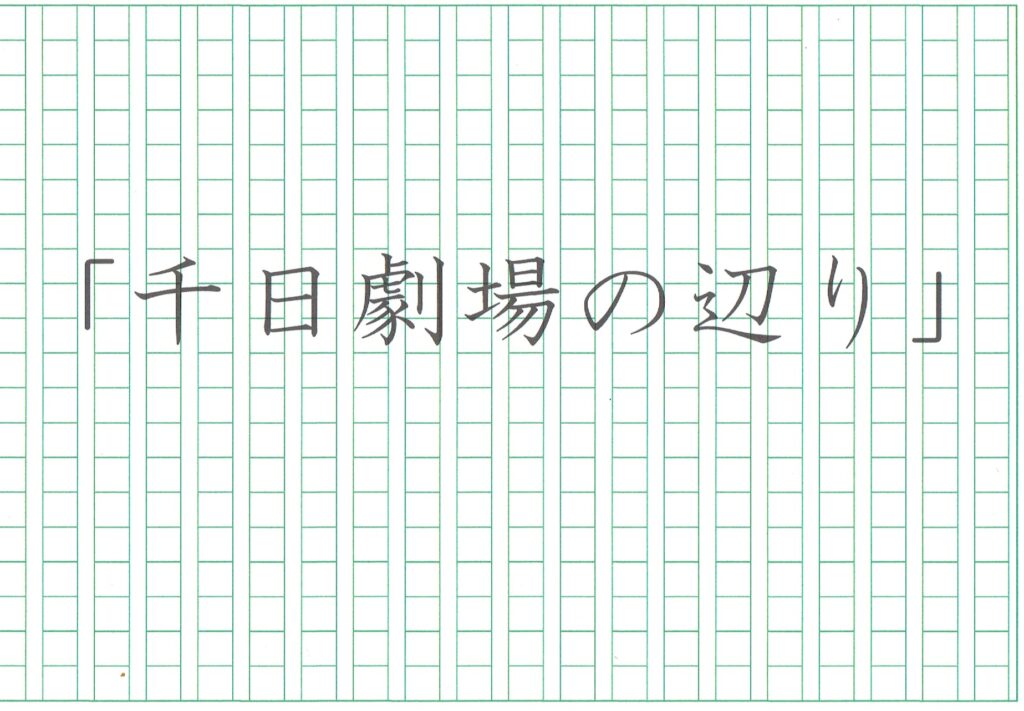
根本 幸江
1
さっきまでの緊張感がまだ頭のどこかに残っていて、もう当分だれの顔を見るのもイヤだ、口も聞きたくない、と思いながら急ぎ足ですべすべした石段を上り地上に出た。
腕時計を見れば、開演までに二時間以上ある。急にもっと旨く話せば良かった、あ、あれも聞いておけばよかった、と気になってくる。所詮たいした仕事でないのに、襤褸ぞうきんのように疲れ果ててしまうのは年のせい。それと、普段、人の多い繁華街などからは離れた場所にいるのに、こんなときばかりは都心に出て美佐江には、ほとんど異星人のように思える年の離れた女たちと話すことになるからだ。
劇場周りに漂う空気には情熱とも諦めともつかないものがある。何年か通い詰めているうちに大方の人は時間のパラドックスの中にはまり込んだようになり、自分が現在どの位置似るのか分からないという、一種酩酊状態になる。まるで麻薬のようなもので、一度はまり込んだら抜けられない。
今日とりわけ妙な気分でいるのは、先ほど正木氏に会っていたからでもある。正木氏の娘、ちさ子さんも一時舞台役者の卵だったのだが、ある日、
「人前で媚びるようなことはさせたくないんだ」
そういって、役者を辞めさせ、もともとの志望だった音大のピアノ科に入り直してピアノの勉強をさせた。正木氏は長年クラシックのファンで、バッハのパルティータを娘の弾くピアノで聴きたいという願望を持っていた。そういうわけで、紆余曲折があったので、音大を卒業した時には、すでに三十も半ばを過ぎていて、今や父親の夢は千日劇場で娘の弾くピアノを聴きたい、そして劇場を人でいっぱいにしたいという、そういうものに変わっていた。
2
それ以上、聞いているのがどうにもつらくなって、正木氏の少し赤くなった顔を見つめていった。アゴのあたりに髭の剃り跡が青々としている。髪は半分白くなっているのだがアゴには白髪は見られない。それがもう六十半ばになる正木氏を若々しく見せている。も 「じゃあ、今日は失礼します」
美佐江が立ち上がった時に、肘が低いガラステーブルに当たり、ガシュッと大きな音をさせた。正木さんは顔を上げ、茶色のくたっとしたショルダーバッグを引き寄せると、中から二つ折りのチラシを何枚か取り出した。
「お知り合いの方に、チラシをお渡し頂けると有り難いのですが。もしお嫌じゃなかったら、皆さんに・・・・・・あ、もう少しどうでしょう」
そういって、正木氏はさらに十枚ほどを鞄から取り出した。
「お願いします」
丁寧に、有無をいわせない調子でいう。
チラシの中では、演奏用に胸の空いた赤いドレスを着たちさ子さんが少し恥ずかしそうな顔で笑っている。一度、父親の紹介で実際に会ったことがある。長身で肘の長さが女性としては長すぎるくらいなのが繊細というよりテニス選手のようで、技巧をこらさずにすーっと立ったところが、いかにも日向に咲く満開のゼラニウムのような大らかさがあり好感をもった。
顔を上げると、長身の娘を見上げる小柄な正木氏のまぶしそうな笑顔と細い目があった。
美佐江は受け取ったチラシを見ながらいう。
「ほんとうにおきれいですね」
「いえ、そんなこともないですよ」
そういったまま、もじもじした様子で、正木氏はそこに立っている。
自分の娘を誰よりも素晴らしい女性だと思っているのは、含羞を含んだ笑顔からも明らかだ。このひとは、いつもこんなに笑っているのだろうか。それとも娘を見ていたり、娘の話をしている時だけなのだろうか。娘を愛しすぎた男を見るとなぜか恥ずかしくなる。そういえば、この人は三十代で亡くした妻をこよなく愛していたとか。ひょっとして娘以上に妻に執着していたのだろうか。
そんな邪念を振り払うように美佐江はいった。
「きっと、今度のコンサートも大成功ですよ。伺うのを、楽しみにしてます」
こんな風に嘘もほんとうもない言葉が、劇場周りでは日に何度もくり返される。相手も分かっていて、素直に喜んだ風をする。たがいにそれ以上傷つかないために。
美佐江は、自分の一番大事なもののために必死になる人を見るのが好きだ。守銭奴みたいに必死になる人が。そして、そんな素振りを少しも見せずに行う人が。つまり一番大事なのは、相手に無理強いされているという気持ちを起こさせないこと、そして負担に感じさせないことなのだ。
3
正木氏と別れた後、美佐江は大通りを海側に向かって歩いていった。まじめな正木氏と会ったあとは。いつも少々疲れてしまう。それは善良な正木氏に自分のいい加減さを見抜かれては困るという怯えに似た感情である。
通りは風が吹いて埃っぽかった。しかも4月にしてはだいぶ日差しも強く、心なしか早足で歩いていたので鼻の頭にうっすらと汗をかいていた。
「こんな暑いところをぶらぶら歩いていたら駄目だわ」
いい聞かせるように自分にいうと古い石造りの大きなビルの側面にぽっかり空いた、洞窟のような地下道の入り口に入って行った。
ビルの地下は薄暗かった。古い石の壁にはところどころヒビが入っていて、天井まで伸びているところもあった。だれにも人に会わなかった。あたりに、ぼんやり薄明かりを点けた理髪上がガラス越しに見えた。美佐江は、このビルが間もなく取り壊しになるという記事を新聞で読んだのを思い出した。まさか、もう取り壊しが始まっているのだろうか。美佐江は急に怖くなり右に折れて、入ってきた方角とは反対の方に急ぎ足で歩いていった。
通路の両側の壁は湿気を帯びていて、水滴でも付いていそうに見える。天井では、ヘリコプターの翼のような扇風機の羽がどこからともなく吹いてくる風に煽られるようにゆっくりと羽を動かしていた。店や事務所にはことごとくシャッターが降りていた。外からの明かりが降り注いでいる階段が左手に見えて、そこを上って行くと踊り場になったところにベンチが置かれ、スーツを着た若い男が座ってパンを食べていた。
美佐江はハッとして足を留めた。男はもっと驚いたようだ。片手にパンをもっとまま美佐江の顔をまじまじと見ている。視線に耐えられず美佐江は訊いた。
「出口はこちらですか」
男はパンを持ったまま微かにうなずいた。本当に訊きたかったのは、「パンおいしい?」「あなたはなぜそんなところでパンなんて食べてるの」ということだった。
4
外に出ると真昼の日差しが明るかった。美佐江はそれを避けるように、建物の陰に沿って歩いて行った。
交差点を渡ると、いきなり大きなガラス張りのビルが現われ、大理石の壁の横に、まるで人形のような変わった形の帽子をかぶりクビに三色国旗のようなスカーフを巻いた二人の女性が座っていた。
どうやらこのビルの案内をしているらしい。後ろには、仰々しいような大きなポスターが何枚か貼られている。美佐江は汗をハンカチで拭きながらそばまで近づいていった。
ポスターには趣ありげな茶碗の写真が並んでいて、茶道具の文字も見える。とても高価な茶碗のようだ。自分には縁がないが、ちょっと見てみたい気持ちになった。
それに開演にはまだ1時間弱あるから時間をつぶすにはちょうどよい。
「これ、どこでやっているんですか」
二十代半ばくらいの案内の女性の一人が顔を上げ、歌うような高い声でいった。
「○○美術館です」
その声があまりに澄んでいて、片耳が少し聞きにくくなっている美佐江にはよく聞えない。
「え、どこですか。どうやって行ったら良いんですか。この茶碗が見たいんですけど」
今度は隣の女性がもう一人に軽く耳打ちすると、白い手袋の手を後ろに向け背後のドアのあたりを指し示した。
「あそこにエレベーターの乗り口がありますから、それに乗って五階まで行って下さい。入場は四時までですので、ご注意くださいね」
「ありがとう。気をつけます」
まあ、そんな遅くまではいないだろう、とは思うが、美佐江はていねいに礼をいってそこを離れた。一度振り向くと、二人の受付嬢は小さな帽子を横に被りさっきとまったく同じ姿勢で座っている。美佐江は壁づたいに歩いて建物の端まで行った。
ここは旧財閥系の名前の付いた美術館の入り口のようだ。美佐江の足は吸い寄せられるようにエレベーターに向かった。
ビル自体は最近、高層のものに立て替えられたが、その中にすっぽりはまり込んだ形で旧い建物が残されているらしい。
5
エレベーター乗り場の手前に小さな宝石店があった。
店頭に手品師のように黒のスーツを着て白手袋をはめた男が立っていた。男の目の前には装置について説明している。
透明ガラスの中に回転盤のようなものが入っていて、それがかなりのスピードでぐるぐる回っていた。何かの実演販売のようだった。男は人々の顔に向かっていった。
「さあ、ご覧ください。ダイヤモンドは何によって削れると思いますか」
若い男は手品師のように両手を広げ思い入れたっぷりにいった。美佐江は困惑し、微かに苦笑しながら見ていた。
一組の夫婦のような男女がその前に立っていて、女性の方がくすぐったいような声をあげ、傍らの男を見上げ耳許で何か囁いた。夫は妻の背中に手をかけて自分の方に少しだけ引き寄せた。その体が固く緊張しているのがわかった。
「そう、ダイヤモンドです。ダイヤモンドでしか削れないんですよ」
男がもったいぶった様子で二人の顔を見て言う。女性が小さくうなずいている。まるで少女のように。少女の心は純粋無垢である。何ものにも傷付けられない。ダイヤモンドが他の石を傷付けることはあるが、自身が傷付くことはない。
「ダイヤモンドはダイヤモンドによってしか傷を付けられないのです」
そうだろう、そうだろうという表情が、二人の顔の上に浮かぶ。ダイヤモンドの刃先によってダイヤの縁が徐々に削り取られていく。見つめている妻の口から細くため息がもれた。
エレベーターで上ったところに入場券売り場があり、美佐江はチケットを買い建物の中に入っていった。 戦前は銀行のホールだったという丸い柱の並ぶ洋館のサロン風の部屋はうす暗く、茶碗などの入ったガラスケースのところどころにやわらかい光が当たっている。見学客は中年以上の女性グループがほとんどだ。みんな茶でもやっているのか一つひとつ熱心に見ている。
中に一人男性の見学者がいて、ボソボソした声で何か話しているのに気がついた。ハンチングを被った上背のある初老の男で、回りを女たちが取り囲んでいる。気になってそばに近づいていった。
「この茶碗はだね……」
男がとうとうと話している。茶碗の由来を語る顔には何かに裏打ちされた自信がほの見えている。皆一言も聞きもらすまいとするように男の口許を見つめ、うなずいたりため息をついたりしている。
6
話は専門的で微に入り細にわたっていておもしろい。それに博学で骨董の知識も深く一つひとつが人の生のような生々流転の末ここにあるのだとよくわかる。茶碗の個性が際だって胸に迫ってくる。 それに男の、骨董が好きでたまらないという様子には見ていて微笑ましいものがあった。美食家が美味珍味を前にしたときのように表情や声、しぐさにほとんど官能的なものが漲っている。
そんなものにも惹きつけられ、男がほかのケースに移動すると女たちもぞろぞろとそのあとをついていった。
室内は薄暗く、ハンチングを被ってマスクをしているので顔立ちや表情はよくわからない。けれど、美佐江にはその男が知っている人のように思える。
「ほう、これは夏向きの『瑠璃霞木立文』冷茶碗ですな。瑠璃はガラスの古名です。ガラスの碗というと最近のものに思えますが、正倉院宝物の中にも異彩を放つ白瑠璃碗がありまして、決して新しいってものでもないんですよ」
男は少し声を高めつつ、ながながと説明している。その声を聞いていて、美佐江はますます落ち着かない気持ちになる。
その時、暗い物陰から紺色の背広を着た職員のような男が近づいてくるのが見えた。職員はハンチングの男の真ん前に立つといった。
「失礼ですが」
「はい」
ハンチングの男は不審そうな顔を向けた。
「何をしてらっしゃるんですか」
「説明してただけですよ」静かな声いった。
周りの女たちのあいだに、ざわざわした空気が広がっていく。
「何よ、この人」
「邪魔しないでほしいわね」
小さい声で不満げにいう声も聞えた。職員は軽く舌打ちしたようだ。
「困るんです。館内でそんなことをされては……うちの美術館でやってることと勘違いされますから」「そうですか」
男は黙った。
「知ってることを話してただけなんですけど……」
「とにかく困るんです。信用問題なんですよ」
男は口をつぐみ、目をあいまいに瑠璃硝子の茶碗のほうに向けた。
どうなるかと固唾をのんで様子を見守っていた女たちもあきらめ、心残り気な様子で男から離れていった。
7
ハンチング帽の男は低い声でしばらく職員と話していたが、やがて頭を下げて何度かうなずいた。職員は顔をしかめたままで、少し男から離れ、軽く全身を眺め回した後、事務室でもあるのか細く薄暗い廊下の奥へ去って行った。
職員が行ってしまうと緊張が去ったのか、男は頭から帽子をとってマスクを外し、ハンカチで額の汗を拭いた。
その顔を見て美佐江は声を上げそうになった。なんとさっきまで劇場横で会っていた正木さんその人だった。正直いえばさっきからどことなく似ている気はしていたが、そんな偶然あるはずがないと心の中で打ち消していたのだ。ひょっとして他人の空似だろうか。
いや、あのちょっと目を伏せた様子とか、ねばっこい話し方は確かに正木さんに違いない。聞いたことのある声だな、と思っていたけれど、やはりそうだったのか。
それからは、美佐江はなるべく顔を伏せて男と目が合わないようにした。目が合った時、相手がどんな表情になるか、そしてそれを見た自分がどんな顔をするか想像がつかなかったからだ。先程の感じでは、正木さんは自信ありげというよりも、どこか弱々しげに講釈している。好きでたまらないから思わず語ってしまっているというように。そんなところがいかにも正木さんらしい。
もともと気の弱い人なのだ。そんな、正木さんが自分の失態?を美佐江に見られたと知ったら居たたまれないだろう。たぶん元の正木さんには戻れないだろう。少なくとも私の前ではと、美佐江は思った。そう考えれば、すぐにここを立ち去ろうかと思う。
けれど妙な好奇心が美佐江をそこに引き留めた。別にいいではないか、悪いことをしていたわけではない。職員に咎められたにしろ、彼の本来もつサービス精神でうんちくを語っていただけだろう。
そういえば、いつか正木さんから、趣味で茶碗を集めていると聞いたような気もする。いや、それこそ、今見たことを過去の記憶に置き換えているだけかも知れない。
そんなことをぐずぐず考えているうちに、離れていた女たちも再びハンチングの男のもとに集まってきた。
「また面白い話をして」
というように、女たちは正木さんの顔を見上げた。陳列ケースの中を見ていた女も、時々気になるように振り返って見ていた。美佐江はなるだけ下を向いて、それでも好奇心から。離れることができず、そろそろと移動を始めた正木さんと、女たちの後について歩いていった。
8
少し遅れて隣の展示室に入ると、ハンチング帽の正木さんを囲む一団は、すでに反対側の壁の方に移動している。こちらの部屋には硝子のショーケースがなく、壁に藤原定家筆の小倉色紙などが並んでいた。その先に能面がいくつか展示されていた。
中央に鼻曲がり中将の面があった。中心からずれた鼻をした歪んだ美男の面である。正面から見ると、どこか寒々しいような哀感のある、けれど決して見るのをやめさせない不思議な魅力のある顔だ。美佐江は前に立つと動くことができなくなった。千年前の霊がふわりと目の前に舞い降りてきたようだ。
また、その面は老人のようでもあった。美男の顔なのに、老人に見えるとはどういうことだろう。その面を見たあとでは、若さというものが美しいとは思えなくなる。濁った皮膚や、年月をへた疲れや、退廃や、唾棄すべきほどのものを見続けたことで、しょぼしょぼと濁った目や、奥におさめきれないほどの哀しみを宿したような顔であった。
少し離れて若い女の面があった。どきりとした。女の顔がそのまま置かれているように一瞬見えたからだ。瑞々しいくらいの美貌だ。口もとに淡い笑みを浮かべている。色艶が表情の隅々にまで漲って春の花のようだ。
そのとき唇の横に何かの跡が血痕のように付着しているのに気が付いた。プレートの解説では、作者の孫次郎は少し前に亡くなった妻の顔を思い出しながらその面を彫ったのだという。ということは、死んだ妻の面差しがほとんどそのまま現れていると思っていいのだろう。顔の造作、表情までも、その面影をひとつひとつ思い描きながらノミで刻んでいったのだろう。
そういえばいつか正木さんはいった。
「妻が亡くなったのは三十半ばの時でした。僕より十二歳も年下でしたからね。残酷ですよ、初老の男に幼い娘一人を残して」
そのとき正木さん、いや、孫次郎の気持ちはどんなだったろう。
深夜など狂おしい気持ちに捕らわれたりはしなかったか。彫り上がった直後、面はきっと初々しい若妻の匂い立つような美しさだったろう。面は何百年ものときを経て、今やどこか恨みがましい様子さえ見せてそこに掛かっている。
少し前を歩いていた正木さんは、どんな気持ちで孫次郎の面を眺めたのだろう。
ふと後ろで声がして振り向くと正木さんである案内人が、宮廷女性の貝合わせの道具の前でまたもや数人の女たちに取り囲まれていた。すると背中のほうからブレザーのようなものを着た今度は若い職員のような女が近づいていくのが見えた。
9
「ここで何をなさってるんですか」
制服の女性はいった。
「話してただけですよ」
正木さんは割にはっきりした口調でいった。
「困ります。勝手にいろんな解説をされては」
「別に解説ってほどじゃないですよ。僕の感想をいってただけです」
ああ、またさっきのやり取りが始まった。
美佐江が好奇心半分で見ていると、しばらく何かいい合ったあと、制服の若い女は納得したように何度か頷いた。正木さんの顔を見上げて笑いかけさえしている。
美佐江は心底驚いた。ああ、あなたまで陥落させられちゃったのね。美佐江は爆笑しそうになりながら、出口のほうに向かった。
それにしてもほんとに変な人だ。そもそも私が正木さんの何を知っていたというのだ。職業も正確な年齢もわからない。ただ、千日劇場の辺りで、しょっちゅう出会う男性の一人に過ぎない。
そして駆け出しのピアニストである娘の売り込みをしている。そんな娘に弱い父親の一人に過ぎない、はずだった。それでは飽き足らず、美術館でうんちくを披露することに、ささやかな喜びを見いだしているとでもいうのだろうか。
正木さんのどこか人間離れした明るさや朗々とした声を思い出していると、エレベーターが上昇してきて扉が開いた。中に入って、階ボタンを押そうとすると、慌てて乗り込んできた男がいた。正木さんだった。
美佐江は気づかれないように、背中を向けている。
1階についてドアが開き、外に出たときに、あ、と正木さんはいった。
「偶然ですねえ」
「驚いた」
美佐江は澄ましていった。
「こんなところでお会いするなんて」
相手の男の顔に何か疑うような表情が浮かんだ。
「見てましたか」
声を聞いて美佐江はゾクッとした。低い弱々しいトーンの声なのに奥に恐ろしげなものが潜んでいる。 美佐江はあいまいにうなずいた。
「ひょっとして、ずっと?」
「それほどでも」
「ああ、やっぱり、あなただったんですね。さっきから、こちらをちらちら伺ってる人がいるなと、どうも気になってたんですよ」
美佐江はハラハラする。
「ずいぶん、お茶碗のことに詳しいんですね」
「それほどでもないですよ」
正木さんは素っ気ない調子でいう。
「お茶の先生ですか」
「まさか、ご冗談を。僕がそんな風に見えますか」
先程の案内嬢たちが、不思議そうにこちらを見ている。
そのまま並んでビルの外に出た。幅のある道路を突風が吹き荒み、大型書店の看板の前を埃が舞っている。その角を少し行って左に曲がった先に千日劇場がある。
美佐江は腕時計を見た。
「大変、開演二十分前だわ」
「じゃあ、急いで、劇場にお戻りなさい」
「そうします。またお会いしましょう」
「そうですね。気を付けて」
通りを風が吹き抜けていく。振り向くと、半分白髪の正木さんは笑うような泣いているような顔でこちらを見ていた。
了









コメントを残す