威子が入内して中宮になり、ついにわが娘たちが三后を占めることに。祝いの席で月を見上げ例の和歌を詠む道長。果たして、どんな気持ちだったのか
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

威子が入内して中宮になり、ついにわが娘たちが三后を占めることに。祝いの席で月を見上げ例の和歌を詠む道長
ついに三后を我が娘がしめ、帝はわが孫。道長にとって、たしかにこれ以上の栄達はありません。
威子が入内して中宮となった日、それを祝う宴が催されます。道長は意識せずとも気分は昂揚し、得意の絶頂にあったでしょう。
そして、空の月を見上げると晴れがましさがつのって、ついにあの和歌を詠みます。

ついに、この世をば・・・ と
この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば
一同、静まり返ったのち、おおー、というどよめきが・・・。返歌を求められた実資。けれど返歌を詠まなかった。この歌にどう返したらいいんだ(__;)・・・と思ったからか。
そして自分が返歌をするより、「みんなで唱和しましょう」と提案。皆さん、どんな気持ちで唱和したんでしょうか。
この夜のことは、例によって実資がきっちりと「小右記」に記しています。けっこう意地悪な気持ちだったのかもしれませんね。

「後世の人は、どう思うかな」
ちょぴり、楽しみに思いつつ、筆をとったか…。笑
まんまと実資のワナに
実資はあまり子に恵まれず、ドラマにも出てきた姫を猫かわいがり。そして財産を全部娘に与えるなど不可解な行動をし、もうひとつ子孫がぱっとしません。一族が栄えに栄えた道長とは対照的なのです。
歴史はこんな意地悪をよくします。聖徳太子(厩戸皇子)の子が根絶やしにされたり、天下人 秀吉になかなか子が生まれなかったり。
人の運は頂点まで達すると、やがて月が欠けるように陰が差しはじめます。道長の場合は、健康的な心配もありますが、ここまで偉くなれば、あとは身を引くしかない。
そんな道長の、表情に表われる若干の不安感を、柄本佑さんは巧みに表現していました。複雑な内面を表すのが、本当にうまいい役者さんだなと思います。

月の光を受けて一人立つ道長を、まひろ(紫式部、吉高由里子さん)はどのような気持ちで見上げていたのでしょう。
そして、まんまと(笑)実資の思惑どおりに、私たち後世の者は道長を傲慢で偉そうで、ちょっとイヤな奴と認識しています。(笑)
今回、出家するという父 藤原為時(岸谷五朗さん)とまひろ(紫式部、吉高由里子さん)のしみじみとした場面も心に残ります。

よくまひろたちは、ここに座って、月を見上げながら家族の会話をしていますね。
こちらは、紫式部の邸跡と言われる旧 廬山寺です。

まさか同じお庭と言うことはないでしょうが、なんとなく、紫式部の気分になってお庭を眺めたりできます。まあ、勝手な感慨ではありますが・・・。笑

今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので目を通していただけましたら幸いです。

清少納言の「枕草子」は今の女性のような感性で書かれている。まるで千年前の端切れが語りかけてくるような・・・ 
12月7日、ショッピングタウウわかばの旧「春」で、懐かしのロックを聴いて青春にカムバック!百軒だな、ウクレレおじさんズがご出演 
クリスマス間近の今は、母親が一番忙しい時期/どの母親だって、愛情かけて悩みながら子育てしてる/二人で歌う「瑠璃色の地球」をきいてみてください 
高畑充希さん、ヴィヴィッドで魅力たっぷりの藤原定子になるだろう。見上愛さんの彰子も楽しみ 内気で健気な少女がやがて強い女性に 
歌好き 踊り好き 集まれ! 「若葉台キッズミュージカル」8/25 ~演出 Yuka 内山明子のピアノに乗せて~


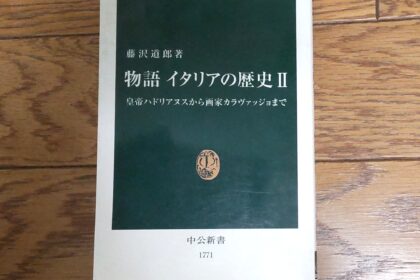



コメントを残す