グリーンベルト (7)
私たちはツアー・モービルに乗ってアーリントン墓地に向かっていた。 なだらかな丘の傾斜地に、見渡す限り白い小さな墓石が点々と並んでいた。
もう金輪際動くのをやめた死者たちは、みなそれぞれ自分の死についてひっそりと思いめぐらしているようだった。大きな木の下では墓石も心もち陰って緑色がかって見える。途中から私たちは乗り物を降り徒歩でいった。
「神の御前のみで名のある戦士たち」と言われる無名戦士の墓のそばで、兵が銃を肩にかけ巡回していた。
向きを変えるときには両かかとを合わせて打ち鳴らす。そのカーンという音が青空に吸い込まれていった。ジョン・F・ケネディの墓の前で「永遠の炎」がちらちらと燃え続け、そのかたわらで、老女が悲痛な顔で花を捧げていた。異国人の私たちがそばに寄るのもためらわれるほどだった。
帰りの道々少しホッとして軽い笑い声をあげると、向かいから来た三人の褐色の肌の男の一人が、すれちがいざまこぶしを振り上げた。私たちは自分たちが軽率だったのに気づいて、ツアー・モービルまで足を速めたわ。本当に何の考えもなかったのよ。
ディストリクト オブ コロンビア(コロンビア特別区)―どの州にも属さない連邦議会の直轄地。ヘレンは日本にいるころ、ワシントンD.C.のD.C.に、特別な思い入れを込めて言っているようだった。
「オー、ノーノー、ディー、スィー」
老人特有のしつこさで口の両端にしわを寄せ何度も何度もいて聞かせるのだった。
「いいわよ、もうわかったわ」
葉子さんが笑いながら言ったけれど、冗談ではない。ヘレンの顔は真剣だった。
ヘレンは当時70歳を超えているのは確かだがだれも正確な年齢を知らなかった。2年前まで私の住む団地のそばに住んでいた。森の中にある数軒の家の一つで、夫のボブさんは近くの大学で英語を教えていた。
平屋建ての小づくりに見える家だけれど、中は広々として居心地よさそうだった。今の家具類はよく磨かれ、台所の鍋や器具類も使い込まれてこざっぱりとしていた。
ヘレンはベジタリアンの家に生まれて自身もベジタリアンだった。だからヘレンの家でごちそうになるときには、小麦や全粒粉、豆などの食材を使った料理が主だった。そうそう、ヘレンが好きなもののひとつに稲荷寿司があったわね。だからよくお土産にもっていったのよ。すると「まあ、うれしいわ」って、とても喜んでくれたものだけど、ちょっと気を遣ってくれてたのかもしれない。
まあ、とにかく、そういうわけで決まった食材の中で工夫して調理するのがすごくうまかった。顔が映るほど磨き上げられた鍋やフライパンを見ていると、質素な全粒粉のパンとか開拓時代の主婦の台所とか、そんなものを連想したものだった。
そして、そんなヘレンに葉子さんはよく言ったものだった。
「ヘレン、あなたはアメリカ人じゃないわ、日本人よ」って。
それを聞いてヘレンがどう思ったかは想像の外よ。だってほかにアメリカ人の知り合いっていないんですからね。
それに何をいっても、私たちはヘレンが大好きだったし、ヘレンのほうでもまた、ちっぽけな島国の日本人たちを愛していたのよ。




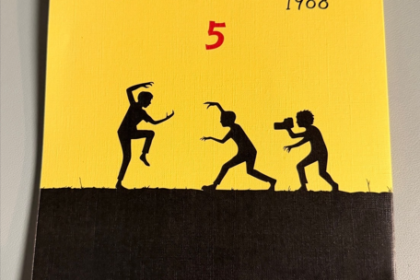




コメントを残す