「穏やかな死に医療はいらない」萬田 緑平著 朝日新書
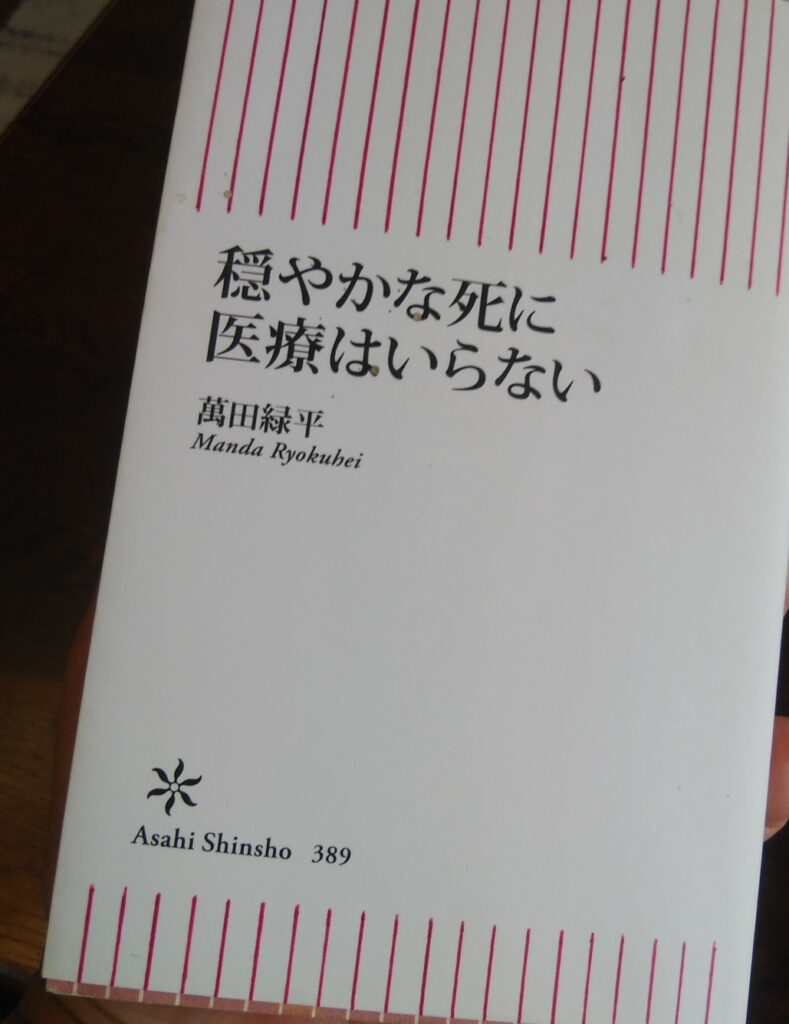
著者は元々、大学病院の外科医として手術などを行ってきた医師。
手術や抗がん剤治療などに当たる中で、終末期を迎える患者に寄り添う道を選びたいと自問し2008年、医師3人、看護師8人からなる「緩和ケア診療所・いっぽ」の医師になる。
自宅で最期を迎えることはできるのか。人として最期まで自分らしく生きるとは、などを改めて考えさせられる。
若いころに、末期がんの患者の担当医師になった。
その際に、がんであることを伝えられずに悩み、患者も疑心暗鬼になって、ついには医師への信頼感をも消失させてしまった体験をもつ。
その後、終末期医療に関心をもち「いっぽ」の医師になって、「自宅で最期まで生き抜くお手伝い」を続けている。 余命1週間の患者を自宅に戻すかどうかで、大病院の医師と激しくやり取りしたことも。
パイプにつながれ、ほとんど意識もないような患者が掠れた声で、
「水が飲みたい、家に帰りたい」
必死に伝える声も聞いた。
「治療中の患者を自宅に帰すことはできない」
と大病院の医師。
「それなら、治せるんですか」
必死で食い下がる筆者。 さらに悪くなると、
「このような状態になっていて、自宅に戻すのは不可能」
けっきょくどの状態であれ、患者の希望は無視され延命治療が続けられる。
家族もそれに反対できない。
それは家には病院のように医療設備もなく、看護にも自信が持てない。家で重病の家族を最期まで看取る勇気もない。
退院したことでより、苦痛を与えてしまうのではないか、最期を迎えるとき、もし自分が気づかなかったらどうしよう、と恐れ、責任感で押しつぶされそうになるからだ。
けれど筆者は、自宅で、多くの患者が心豊かに、安らかな死を迎える姿を目にする。
好きなゴルフをやりたいと退院した人。
管につながれていた患者が家に帰って晩酌を楽しみ、風呂に入れてもらって、満足して死を迎える姿も。
また、ある女性は居間に寝台とピアノを置き、ときどき好きな曲を弾いて、子どもたちに囲まれておだやかな最期を迎えた。
いよいよお別れの時、大切なこととは?
それは家族が、寄りそって、感謝の気持ちを伝えることだという。
「まだ、がんばって」ではなく。
その人はもう充分がんばったのだ。
「これまで、ありがとう」 「さようなら」
それで十分なのだ。
感謝のことばを伝え、家族の絆をもう一度確かめる。
それこそ旅立つ人にとって、人生を価値あるものにしてくれる最高の言葉なのかもしれない。
五年前、父のいまはの時その手をにぎり、
「行かないで」と叫んでいたわたし。
それを悔やんでいる。父に哀しみをあたえてしまわなかったか・・・。
今なら、きっと「これまでありがとう」といえたのに。
家族の介護をしている人、みんなに読んでほしい一冊。

「老人支配国家日本の危機」 エマニュエル・トッド 
おもしろい本です、と言っていただき感謝です!!「若葉台団地 夢の住まい、その続き」 
13日のべらぼう、見所は武元と意次が見つめ合う迫真の場面。武元は「ただの白髪眉」でなかった。そして生田斗真さんは、鎌倉殿の13人に続きまたまた人でなしの役(__;)いえ、熱演に感動しました 
錯乱の源内(安田顕)が罪を犯して牢につながれるという展開に。蔦重(横浜流星さん)の依頼した戯作が原因だったのか・・・ありあまる才能の悲劇ともいえるようなつらい回でした 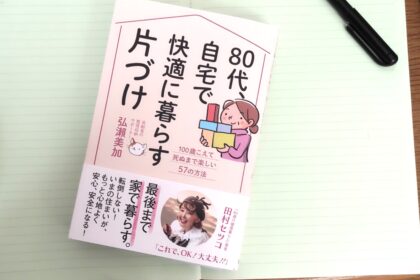
「80代、自宅で快適に暮らす片づけ」(弘瀬美加) 最後まで我が家で・・・そんなシニアの切なる思いに答えてくれる本です





