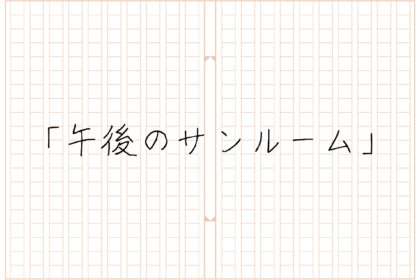ツグミ団地の人々 〈苦い水 7〉
「あんたたち、ママに叱られるよ」
タカ子が大声で叫ぶ。
「へいきだよ」男の子が大きな声でこたえる。
母親たちもまったく気にする様子がない。
「雑巾かモップを貸して」
美佐子から雑巾二枚を受け取るとタカ子は立ち上がり、文句も言わずに店の床を拭き始めた。
「悪いわね」
「平気よ」
タカ子は振り向くと、子どもたちのほうをちょっとにらんだ。
タカ子は黒髪が豊かで、長身のほれぼれするようなスタイルの持ち主である。顔はどちらかというと、べちゃ顔で眉と口の間が狭く目も一重だったが色白で子供のように愛嬌がある。三歳の時からツグミ団地で育ったというが、街区が違うせいか初めてこの店で知り合ったのである。
何を聞いても笑ってしまうかして、人の言うことなどろくに聞かない。職場はここからほんの百メートルほど先の通り沿いにあるが、しょくばにいるよい。なぜか職場にいるより、この店にいるほうがずっと長いようだ。
「もう戻らなくて大丈夫?」美佐子が心配して聞いても、
「夕方まで指名のお客がこないのよ。うちは予約制だから」
などと言って、一向に急ぐ気配を見せない。粘って、二、三時間も冷めたコーヒーをすすっていることがある。
「ありがとう。助かったわ」
雑巾を受け取ったときに、豊かな髪から漂ってくる植物系というよりもっと郷愁を誘われるような日向臭い匂いに気がついた。
「どんな香料が入ってるの」
「木のエキスよ」
鴉の濡れ羽色ならぬ、しっとりと重たい髪をかたむけて手でひと筋すくいながら、ふっふと笑う。
「まるで」
「まるで、なんですか」
「杉の木の脂のようなにおいだな、と思って」
気にするかと思ったのだが、
「うちの店の試作品なの。コンディショナーではなくて、頭皮に直に吸い込ませてるの。タブに原液を入れて、泡立たせ、頭をこんな風に」
と頭を思い切り後ろにのけぞらせた。
「泡の中に頭全部を浸すんですね。それでぶくぶくと泡立て、刺激をあたえつづけると、毛穴全部が開いて、汚れが次々と出てくるんですね」
「そうですか、すごいですね」
少し離れた席から平八がタカ子の波打つ黒髪をびっくりしたように見つめている。
「さらに・・・・・・」タカ子は構わずあとを続ける。
「木の香りに包まれることでリラックスして、頭皮だけでなく、頭の中の老廃物も、自然の木の作用で抜け出してくるの」
「老廃物ですか?」
「ええ、死んだ細胞とか、人が生きている中で自然にため込んでしまう老廃物とかね」
「ストレスがたまりやすいですからね、現代人は」
「あたしもストレスだらけなんですよ」
タカ子が長身の身体をくねらせて言った。