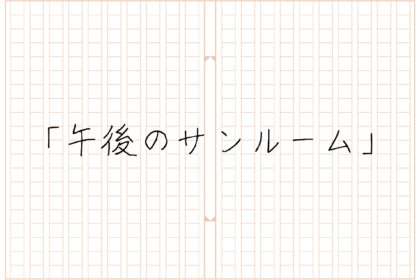ツグミ団地の人々〈レモンパイレディ6〉
母さんはそのころテープ起こしの仕事をしていた。
毎日テープレコーダに耳を近づけるようにしてその音を聴き取っていた。15センチもないようなテープレコーダに耳を押しつけて眉間にしわを寄らせた母さんは、もう百年も生きているおばあさんのように見えた。
少しして、頭をふると、おもむろにバッグの中から分厚いメガネを取り出してかけた。まるで、それによって声まで聞き取れるのだとでもいうように。
カーテンを開けると、シッとふり返る。風の音がうるさいといって、窓を開けることさえしなかった。毎日少しずつ原稿が書きためられていった。おじいさんのような細い声の人と、とがったような女の人の声、ちょっとどもる感じの低い男の人の声。
「えー、それで・・・お集まりいただいたしだいで・・・・・・」
「今の子供たちを取り巻くじょうきょうは・・・・・・」
「決して働く意欲がないわけではなく・・・・・・」
「希望をすててはいけないと思うんです・・・・・・」
僕はいきなり、「腹へった」と話しの中に割り込んでいく。
母さんは、めがねを鼻のあたりにまで下げ、びっくりしたように見つめる。そういえば息子がいたのだと、思い出したように。
そしてあきらめた顔でペンを置くと、台所に行って夕食の支度をはじめた。
くるみもすばやくついて行った。そして、あちこちに首をつっこんでは母さんに叱られていた。やはり気に入りは、母さんのくるぶしをかむことだ。
「いたっ!」
母さんが悲鳴をあげる。手でさっと払いのけたので、くるみは2、3メートルも飛んでいった。
「だめでしょう。お母さんの足をかむなんて。何度いったらわかるの」
しょげた様子のくるみに母さんが、こんこんとさとしていう。くるみに向かって、「母さん」というたびに、僕は猫と兄弟になったような妙な気分になったものだ。母さんはともかく、くるみが母さんを本物の母親と思っていたのは確かだ。
くるみはかまってもらえないのが悔しくて、母さんが台所に立つと、母さんの足のまわりをくるくる走りスリッパを引っぱってぬがそうとする。
母さんは仕方なくくるみの気に入りのタオルを食器棚の上にしき、その上に乗せてやる。まな板の上で包丁を使って切ったり、野菜を洗ったりしている手元を見ているとようやく安心するらしく、いつのまにか目は細く閉じて、こっくりこっくりと居眠りをはじめる。
母さんは笑っていう。
「かわいいわね。眠っていると」
子守唄でも歌ってやりたそうな顔だな、と僕は思う。
「最近、お父さん、帰りがおそいのよ」
母さんはふいに、流しのほうを向いていう。
「前はあんなに早く帰ってきたのに。家の食事がおいしくないのかしら」
「そんなことないよ。おいしいよ」
僕は半分お世辞でいう。