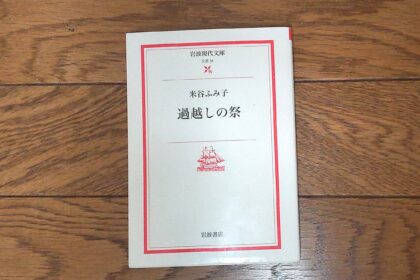抜け道 (1)
――じゃあ、いったい俺はだれなんだ。
――あなたさまですか・・・・・・? あなたは、あたしのいい人でございますよ。
うっすらと笑いを含んだ顔が目の前にあった。陰った座敷の奥で顔は徐々に白さを増し、幼女のように澄んだ二つの目がじっと彼の上に注がれていた。その細い両肩をつかんで、激しくゆさぶってやりたい衝動を彼はこらえた。
目覚めると、頭の上の方に鳥の声を聞いた。ギーイ、ギーイと絶え間なく鳴いている。朝の陽が、ひと雫の水のように雨戸の隙間から入り込んでいた。
彼はその時、またあの夢を見たことに気がついた。両掌にじっとりと汗をかいている。
しばらくして、片膝を立てて起き上がろうとしたとき、空気のゆらぎに似た眩暈の感覚が、頭の後ろ側を通り過ぎていった。
その日はちょうど、月半ばの十五日であった。
彼は顔を洗い、口をすすぎ身を清めると、庭先に下りて榊を数本切り取ってきた。神棚の水を替え、榊の枝先をそろえて供えると、改めて姿勢を正して神棚の前に立ち、柏手を打って家内の無事を祈る。
彼がこの家を継いで以来、何十年もくり返してきた所作だった。
けれどもその朝、頭を垂れ両眼を閉じた彼の脳裏には何の願いも浮かばず、それどころか年来念じてきたことさえ、昼日中の霧のようにきれいさっぱり頭の中から消え去っていた。
彼は怪しみながらも、そのまま姿勢を崩さず数歩後ろに下がった。
考えれば月はじめの一日も先の十五日もそうであった。先祖が神主であった彼の家の習慣にしたがい、父親のしていた形を真似てはいるが、久しく何も願わない日々が続いている。
榊や水を乗せるのに使った脚立を部屋の隅に寄せつけると、台所に行って湯を沸かし、汁や漬け物、買い置きの佃煮などで、簡単な朝食をあつらえて食べ始めた。
梅雨明けの時期特有のムシムシする陽気のせいか、彼はこのところだいぶ食欲をなくしている。
茶を飲み終えるとすぐに食器を台所に運び、ついでに電気釜の蓋を開けてみると、一合だけ炊いた飯が、釜の底の辺にこびりついているのが見えた。
しゃもじでいい加減にかき集めて小ぶりの丼に移し、釜には薬缶の残りの湯を注ぎ入れた。
茶の間に戻り、座卓の前にあぐらをかいて座った。西向きの出窓の外には四十六時中よしずを張っていて、座敷内は日中もうすぼんやりと暗い。
彼の母親は生前畳が焼けるのを嫌い、梅雨明けからすぐに、彼にいってそれを納屋から出させ、庇の下に張らせていたものだった。
目の詰まったよしずの隙間から、気の早いアブラゼミの声が入り込んでくる。家の裏手に檜や楢などの雑木が残っていて、例年どこよりも早く蝉が鳴き始めるのだ。
ジリジリとした鳴き声を聞いていると、明け方に見た夢をいやにはっきり思い出し、空気のぶれるような感覚がまたもや頭の後ろをスーッと通過していった。
彼は立ち上がると、テレビのスイッチを入れた。何人かの男や女が並んで、しきりと口を動かし話している。どれもが早口で、彼にはぎーぎーと機械が鳴っているように聞こえた。
一人が甲高い声で何かいうと、そこにいた人間たちが一斉にどっと笑った。
彼は笑わなかった。何がおもしろいのか少しもわからなかった。聞いているうちに頭痛がしてきた。
手を伸ばして、新聞や書きつけの類やめがねケースやらをあちこち移動させてコントローラーを探し当て、それをテレビに向けるといろいろな操作ボタンを押したあとで、ようやく画面を消した。