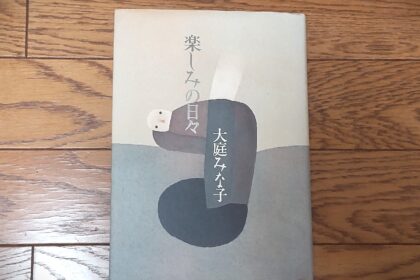千日劇場の辺り ―奇妙な案内人〈2〉
それ以上、聞いているのがどうにもつらくなって、正木氏の少し赤くなった顔を見つめていった。アゴのあたりに髭の剃り跡が青々としている。髪は半分白くなっているのだがアゴには白髪は見られない。それがもう六十半ばになる正木氏を若々しく見せている。も 「じゃあ、今日は失礼します」
美佐江が立ち上がった時に、低いガラステーブルに当たり、ガシュッと大きな音をさせた。正木さんは顔を上げ、茶色のくたっとしたショルダーバッグを引き寄せると、中から二つ折りのチラシを何枚か取り出した。
「お知り合いの方に、チラシをお渡し頂けると有り難いのですが。もしお嫌じゃなかったら、皆さんに・・・・・・あ、もう少しどうでしょう」
そう言って、正木氏はさらに十枚ほどを鞄から取り出した。
「お願いします」
丁寧に、有無をいわせない調子でいう。
チラシの中では、演奏用に胸の空いた赤いドレスを着たちさ子さんが少し恥ずかしそうな顔で笑っている。一度、父親の紹介で実際に会ったことがある。長身で肘の長さが女性としては長すぎるくらいなのが、繊細というより伸び伸びしていて、技巧をこらさずにすーっと立ったところが、いかにも日向に咲く満開のゼラニウムのような大らかさがあった。
顔を上げると、長身の娘を見上げる小柄な正木氏のまぶしそうな笑顔と細い目があった。
美佐江は受け取ったチラシを見ながらいう。
「ほんとうにおきれいですね」
「いえ、そんなこともないですよ」
そういったまま、もじもじした様子で、正木氏はそこに立っている。
自分の娘を誰よりも素晴らしい女性だと思っているのは、含羞を含んだ笑顔からも明らかだ。このひとは、いつもこんなに笑っているのだろうか。それとも娘を見ていたり、娘の話をしている時だけなのだろうか。娘を愛しすぎた男を見ると、なぜか恥ずかしく目を逸らしたくなる。その時の正木氏の顔も必死すぎて、美佐江は切なくなる。
それを振り払うように美佐江はいった。
「きっと、今度のコンサートも大成功ですよ。伺うのを、楽しみにしてます」
こんな風に嘘もほんとうもない言葉が、劇場周りでは日に何度もくり返される。相手も分かっていて、素直に喜んだ風をする。たがいにそれ以上傷つかないために。
美佐江は、自分の一番大事なもののために必死になる人を見るのが好きだ。守銭奴みたいに必死になる人が。そして、そんな素振りを少しも見せずに行う人が。つまり一番大事なのは、相手に無理強いされているという気持ちを起こさせないこと、そして負担に感じさせないことだ。