玉木屋の女房 〈17〉
少年は、彦次郎といった。小柄だから幼く見えるが、数えで十四だいう。
彦次郎はよく働いた。朝は来る早々、仕事場の掃除をし、それが済むと作治の隣にしゃがんで、手許を見つめ、「おい、木くずを片づけてくれ」
そう言われるとすぐに立ち上がって手許箒を取りに走り戻ってくると親方の邪魔にならないようにやはり横に座って由良もいる手許を真剣な目で見つめている。
ゆらもこの少年が気にいったらしく、何かあるとすぐに、「彦さん、彦さん」と呼びつけて、昼のまかない用の油揚を買いに行かせたりした。
多江は、義母の気持ちが安定しているのを見てホッとしている。父の清吉が亡くなってから、この吉原出身の母親には夫が亡くなった哀しみと、
「吉原の遊女なんかを嫁にするから、命を縮めたんだよ」
そんな風な白い目で見られて心の安らぐ暇がなかったのだ。作治と彦次郎が作業部屋で黙々と彫る作業をしている。ただそのことだけが、この家を家庭のようにさせている。不思議なことだった。まるで、作治と彦次郎がすでにこの家の家族ででもあるかのように。
シュウシュウッと木を彫る。こんな風にして仕事をやる。その音が粛々と続いていくのだなと思った。
作治がいつやめるか、いつやめるかと思っていたのに、弟子と呼べる少年まで連れてきてくれたのだ。新しく次に繋がるものができたのだ。
それは嬉しいことに思えた。そんな二人の姿を見ていると、いつか青本や黄表紙の出版に没頭していた亡き夫の姿を思い出すのだった。
売れもしない戯作を持ち込んできて、大いばりで出版を持ちかける侍崩れの男、信じられないほど女の顔を見にくく描く男。そんなしょうもない連中にも清吉はいつだって丁寧で、そんな者たちの中に凄い才能を見つけたがっていた。
「いつか俺が育てた作家だって大いばりしてえのさ」
理想ばかりの清吉に比べて、ゆらは現実的だった。
「おまんまが食べられなきぁゃ仕方ない」
これが口癖なのだ。
売れない戯作者の持ち込んできた話を前に、じっとり脂汗をかきながら文字を追っている清吉。
団扇であおいでやりながら、おゆらはじっと夫の様子を見ている。酷暑の中、夫の身を案じる気持というよりもこれで、また売れない本を作る羽目にでもなってしまえば、今度こそ玉木屋は終わりだ。夫と自分と、多江と三人が食い詰めてしまう姿が浮かんで、一刻も夫のそばを離れることができなかったのである。

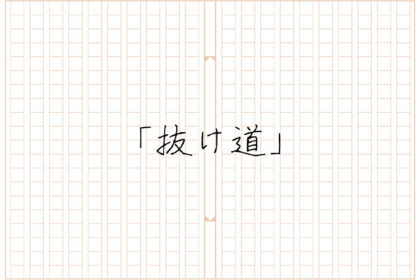
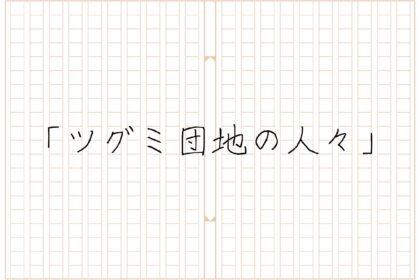
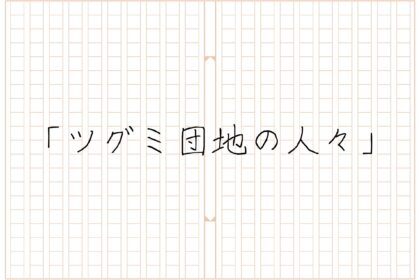
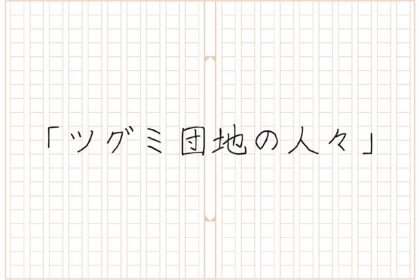

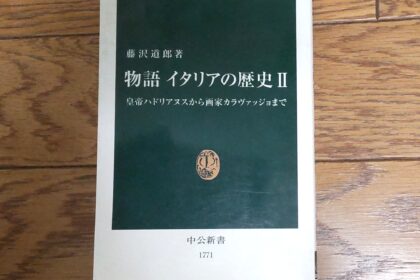



コメントを残す