紫式部の一人娘 賢子はのちに女院彰子のもとで宮仕え 母と違って宮中で恋多き女だった
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

光る君へ。
前回、まひろ(吉高由里子さん、紫式部)がいよいよ宣孝と結婚ということになりました。
実際にも藤原宣孝と結婚し二人の間に女の子も生まれました(999年頃)。
まあまあ幸せな結婚生活のようでしたが、長くは続かず夫は3年ほどで亡くなってしまいます。その後、娘の賢子(かたいこ、大弐三位)を女手ひとつで大切に育てました。
『源氏物語』にはよく、女の子が出てきます。紫の上、明石の姫君、みんな可愛いのはやはり女の子の母親だったからでしょうか。
賢子は18歳ごろに、紫式部もつかえた女院彰子のもとに出仕します。
宣孝に似た明るく華やかな性格だったようで、宮中を舞台にはさまざまな恋愛話があったようです。
そして後に、道長の兄 道兼の息子と結婚します。これについて、いろいろな疑問がでてくるようです。
「なぜ、祖母のかたきと結婚できるの?」と。
ドラマでは、まひろの母が道兼にころされますが、あくまでドラマの中だけのことで、道兼が実際にそんなことをしたという記録はありません。
気にはなりますが・・・。
こちらは紫式部の邸あととされる廬山寺のお庭です。

6月頃からアヤメが咲き始めます。紫と白い石の対比に風情があり紫式部のやしきあとにふさわしいですね。
そして、石碑に刻まれているのは、小倉百人一首に入っている紫式部と大弐三位の歌碑です。
めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に雲がくれにし夜半の月影 紫式部
有馬山ゐなの笹原風吹けばいでそよ人を忘れやはする 大弐三位
母と娘の歌、それぞれに語感がよく、理知的なところが共通していますね。やはり親子だなぁという気がします。
紫式部は、『源氏物語』を書きながらどのように娘を育てたのでしょう。ドラマの中ではどう描かれるのか、この辺りも気になります。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。

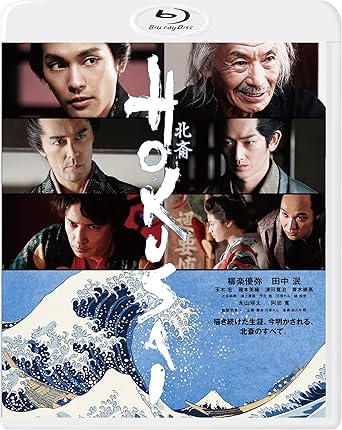


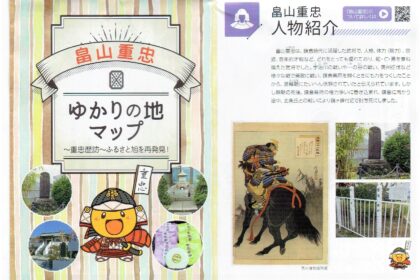




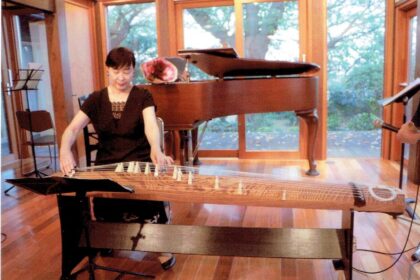

コメントを残す