玉木屋の女房 2
「実はねえ」
両手で茶碗を囲むようにして茶をすすると、お静は笑って言った。
「今日は、多江ちゃんの結婚話を持って来たのよ。とんとなら、もっと明るい時間にきて話すといいんだけど」
「まあ、お店がありますものね、仕方ないですよ」
ゆらは愛想良く答えるが、どうせろくな話ではないだろう、と内心思っている。この前なんて、自分とこのそば屋の下働きを紹介するのだからゆらは驚いた。
夫の清吉が生きていたら、怒って怒鳴りつけたかもしれないが、母と娘の寂しい二人暮らしなので、思っていることは心の中に呑み込み、なんでも、はいはいと聞いておくにこしたことはない。
清吉は、気難しく頑固な男だったが、少なくとも無神経ではなかった。おおざっぱに見えるところが、逆にひとの警戒心を解き信頼されたのだ、と多江は思う。
そのとき、店の奥から近づいてくる足音がして、暖簾の向こうに、作治の顔が覗いた。
「おかみさん」
「どうしたんだい」
ゆらが顔を向ける。作治はお静の方へ、ちらっとイヤそうな視線を向けたあと、ゆらに向かって言った。
「版木がそろそろなくなりそうなので、どっかから手に入りませんかね。蔦屋さんから、急ぎの仕事がくるよ、ってさっき使いの者が」
「おや、そうかい、そりゃあ、ありがたいねえ。蔦重が忙しいってことは、そのおこぼれでこっちまで仕事が回ってくるってことだからねえ」
「へえ、そういうことで」
「明日、版木の方も、手に入るか蔦屋さんに聞いてみておくれ」
「おかみさん、勘弁してくだせえ。明日は、急ぎのがひとつ入っていて、手が離せねえんで」
「そうかい、わかった。あたしには、歩いていくのは無理だから、多江に行ってもらおうかね。あの娘は、蔦谷さんに気に入られてるから」
清吉は、小さい頃から器量よしだった多江が自慢で、どこにでも連れ歩いたのだ。それで、商売仲間のみんなに可愛がられたものだった。まま母のゆらが嫉妬するくらいに。
「わかりました。そうしてもらえると有り難い」
そう言って律儀に頭を下げると、また、ちらっとお静のほうにイヤそうな視線を向ける。
作治には、お静がくるたび、嬉しそうに顔をほころばすゆらが不思議でならない。
「なんだっておかみさんは、あんな女を気軽に家にあげるんだ」
言わないまでも、作治の顔にはそう書いてある。
作業場に戻っていく彼の後ろ姿は不機嫌そのものだった。背中は右側の筋肉が盛り上がって瘤のようになっている。それは、常にかがみこみ、板の機嫌を見ながら彫っている彫師の誇りが固まったようなものだ。



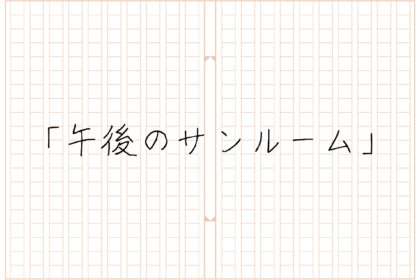







コメントを残す