抜け道 (18)
数百年前、このあたり一体はアラカシやシラカシの深い森であったそうだ。いずれ彼がいなくなれば、家の庭も本来の植生に戻るのだろう。彼の先祖たちは、そういった森の奥でかしこまって頭を垂れたのだろうか。少々いびつな頭をして、それを密かに恥じながら。
彼の顔にうっかり笑みが浮かんだらしい。嫁さんが不思議そうに彼の顔をのぞき込んだ。彼は、自分が母親と妻の記憶の中だけに生きてきた気がしている。その記憶はやわらかな果実のように彼を包み込んで、彼一人を地上にとどめ置いていた。
「そうだわ」嫁さんは急に向き直った。
「おじーちゃん、ちょっと待っててくださいね」
そういって自分の家に走り、ビニール袋に入れたものをもってきた。
「これ、食べられますか」嫁さんはいった。
「シュジンがこの前の日曜に釣りに行って。うちの子たちは、もう見向きもしないんですよ」
袋を開けると、笹の葉の上に二匹の鮎が、黄色みを帯びた腹を見せて並んでいる。
一匹が大きく、一匹が小さい。大きい方は、口からえらにかけて、血こごりをつけている。
「ああ・・・・・・」
何かいったつもりだが。嫁さんには聞こえなかったようだ。
彼はじっと二匹の魚を見ていた。
妻はある日、鮎に鼻を近づけて、西瓜の匂いがするといった。生まれてすぐに母親を亡くし、小さい頃から包丁を持ったので魚を捌くのもうまかった。彼の母親は、魚をさわるのが苦手である。特に鮎はぬるぬるするといって嫌った。
ある日、海沿いに住む知り合いからイナダの立派なのをもらった。妻はそれを二枚におろし、切り身にして醤油とゆずの中につけ込んだ。翌日の夕食時に供され、翌々日の夕方に彼が「あれを・・・・・・」というと妻は首を横に振った。魚はもうなくなっていた。妻と母親は、昼には二人並んで食卓につき、たっぷりと昼食をとるのだ。
「今日ねえ・・・・・・」
嫁さんが同居してる姑のグチをいう。
「感覚が、古いのよ。娘たちの部屋にも、いない間に勝手に入って、いろいろいじったりするものだから、いやがって。あ、そうそう、この前なんか・・・・・・」




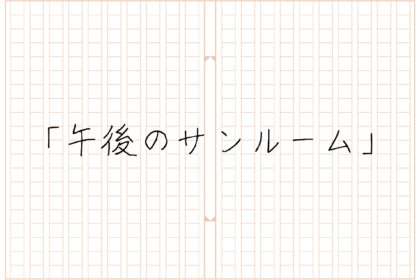





コメントを残す