玉木屋の女房 〈6〉
蔦屋から急ぎの仕事が入ったのはその数日後のことだった。ゆらが店の横にある工房に行くと、作治がいつものように背中を丸めて熱心に彫っている。しばらくそれを眺めていて、ふと、手を休めたとき、ゆらはその背中に話しかけた。
「忙しいところすまないねえ」
作治が汗をかいて赤くなった顔を上げる。
「おかみさん、どうしなすった」
「実は、さっき、蔦谷さんが、新しい役者絵の彫りを何枚か頼みにきたのさ。でも、今他の仕事もあって、あんたに頼みにくくて」
「いや、結構なことじゃないですか。ちょうど弟子代りに、小僧を頼もうと思ってたところです。でも、ちょっとやそっとで役に立つようにはなりませんが、いずれ店を大きくしたときのために」
「今もそんなことを考えてくれてるんだねえ」
ゆらは、有り難かった。玉木屋がいまも続いているのは作治のお陰だった。そんな作治を慕って多江もいずれ、黄表紙の作家や絵師をいくつも抱えた版元になりたいと思っている。いつか・・・・・・、この言葉を心場襲い心のよすがに、あたしも多江も、この作治さんもやってきたのだ。
「ところでねえ、おかみさん」
「なんだい」
「次の仕事にかかるのは有り難いんだが、良い版木がねえんですよ。残ってるのはちっともダメで、思ったような線が出ねえんですよ」
「困ったねえ」
前から使っていた版木屋は、こちらが女の工房だと思って甘く見てるのかどうか、このところ、いくら言っても納品しようとしない。きっと、大きな版元関係のほうに先に回してるのだろう。作治が地道でまじめ過ぎうるくらい丁寧な仕事をしていて、注文が増えるかと思うと、問屋関係から何かと妨害が入るのだ。
「あたしは、このとおり脚が悪いから、探すのも難しいんだ」
「いえ、あっしが、不甲斐ないばっかりに」
「そうだ」
ゆらは、パンと手をたたいた。
「じゃあ、蔦屋の旦那にお願いしてみよう。何、多江に行かせればいいさ。蔦谷さんも、頼まれてる仕事を早く納めてほしいようだったから、嫌とはいうまい。それに、あの娘は小さいころから蔦屋さんに可愛がられてた。家の人がよく日本橋通油町にある耕書堂まで連れていくと、蔦屋の旦那さんが、駄賃だよ、といって必ずお菓子をくれたものだった。そうだね、そうしよう」
ゆらは晴れ晴れとした顔になると、そのまま急ぎ足で奥の座敷の方にいった。その足音が不思議なほど聞えない。それが花街で踊りをやっていた名残なのだろうかと作治は思うが、無論損なことはひと言だっていったことはない。
亡くなった清吉が言っていたのだ。
「あいつは足音を立てない女なんだよ」
「へえ」と言ったきり作治は黙った。主の言葉が女房を自慢してるのか、ただ一つの不満なのかは今もってわからない。









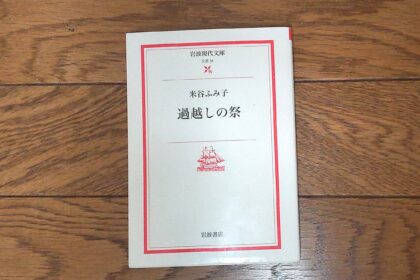
コメントを残す