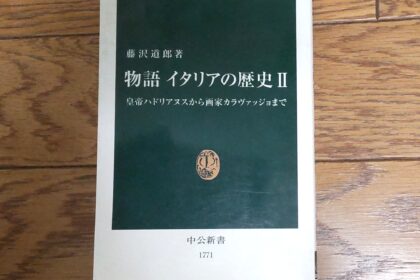清少納言の「枕草子」は今の女性のような感性で書かれている。まるで千年前の端切れが語りかけてくるような・・・
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

「光る君へ」では、中宮定子のこともかなり取り上げられるのだろうか。気になって清少納言の「枕草子」にあらためて目を通してみた。
最初から、「春はあけぼの・・・・・・・」と、朗々として歌うように美しい。
また全体を通して明るく前向きである。それなのに、どことなく暗さも感じてしまうのは結局、背景を知ってしまっているからだろう。
清少納言が定子サロンで才能を発揮し得意の絶頂にいながらも、一年あまりの内に彼女のご主人の上に悲劇が訪れるのだ。昼の光が一瞬にして陰りネガになるように。
「枕草子」の魅力は、そんなところにも理由があるのかもしれない。また、千年前の女性の考えを身近に感じられるのも枕草子の魅力だ。
また布地の感覚、手触り、そして生き生きした女性の感情が、手に取るように目の前に再現される。

《第二十六段》
心ときめきするもの
雀の子飼ひ。稚児遊ばする所の前渡る。
よき薫き物たきて、一人臥(ふ)したる。唐鏡の少し暗き見たる。
よき男の車停めて、案内問はせたる。
・・・・・・・・・・・・・・・・
「よき薫きものたきて、一人臥したる。唐鏡の少し暗き見たる。」
いいですよね。よき薫に包まれて独り寝する心地よさ、なんてステキなひとときなのでしょう。心がときめきます。
そしてまた、「唐鏡の少し暗き見たる。」には、なぜかドキリとさせられます。
鏡の向こうに清少納言の顔を実際に見ているような錯覚にとらわれるからです。その息づかいさえ感じられるほどに。なんて、すごい感性なのでしょう。

《第二十七段》
過ぎにし方恋しきもの
枯れたる葵。雛遊びの調度。
二藍、葡萄染などのさいでの、押し圧されて、草紙の中にありける、見つけたる
・・・・・・・・・・・・
思い出の中に残るものを並べていますね。
「枯れたる葵」とは葵祭のときの葵の葉のことでしょうか。人形のお道具というのもわかりますね。
ところで、「葡萄染などのさいで」とは・・・?
布の端切れのことのようです。本を開いて見ていたら、栞がわりに挟んでおいた端切れが押しつぶされた状態で見つかったのでしょうね。
この端切れも不思議に生々しく、まるで手に取るように感じられます。端切れが千年の時をこえて、私たちの手許に届いたような感覚になります。
なぜそこに挟んだのだろう、そう思って清少納言はその部分をしみじみと再読したかも知れませんね。
それを現代の私たちが、目に見えるように感じるとは・・・・・・。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。



DSCF2430-420x280.jpg)