終活でも、どうしても捨てられないものがある~初めて小説を書いたあの頃

こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。
終活とよく言われる。
終活しなければ、と日々思う。でも進まない。
今日も知り合いの間でその話題が出た。結局向き合いたくないのかもしれない。自分がいなくなるという現実に。
ほんとうに、ほんとうに自分の最後はどうしたいのだろう。はっきりした考えがない。
正直いえば、自分はどうでもいいのだ。
死ねば無問題だから。せいぜい、わずかばかりの残ったお金で、ささやかな家族葬ぐらいはあげてもらえればいい。
それほど、深刻に考えることじゃない。そう考えれば気楽だ。あとは最低、残った家族が困らなければいい。
あと、やらなければいけないのは、残った紙やノートを処分すること。
若い頃から、思いつくままに駄文を書き散らかしていた。今となっては恥ずかしいしろものだが、その頃でなければ絶対に書けなかったものもある。
元群像編集長 橋中氏の教え
30年ほど前、横浜の朝日カルチャースクールに通いはじめ、元群像の編集長 橋中雄二氏の教えをうけた。
初めてまとまって書いた小説の題名は「白い箱の中で」。
今では、気持ちよく暮らしている高層団地の住まいだが、引っ越してきた当初、息苦しくてものが飲み込みにくくなったり、いろいろあった。
そんな気持ちや家庭の悩みなどを書いた。
橋中氏に最初に言われたことばは、
「リアリズム風なのに観念的」
そして、少しして、
「感じの良い文章」と。
きっと少しは、ほめてあげようと思われたのだろう。
さらに、
「感受できるが、表現力が足りない。感受したものをただ並べるだけでなく、スナップショットで並べる。強ければそれぞれが浮かび上がってくる」
なるほどなるほど。
「エピソードを並べるだけ、心の動きがない。もう2回書き込まなくては」
気落ちしめげていると今度は、
「隠忍自重というか緊張感が生きている。主人公は外に出さない賢さで生きている。どうしようもない境遇にあるにしても、どろどろした文章でなく、理性的」
などとと、持ち上げてくださる。
長く文芸誌の編集長をしていた人の言葉には重みがある。そして、褒めてもらっていると調子づいてまた書いてみようかな、という気持ちになる。実は、褒めるしかなかった、ということもあるかもしれないが・・・・・・。
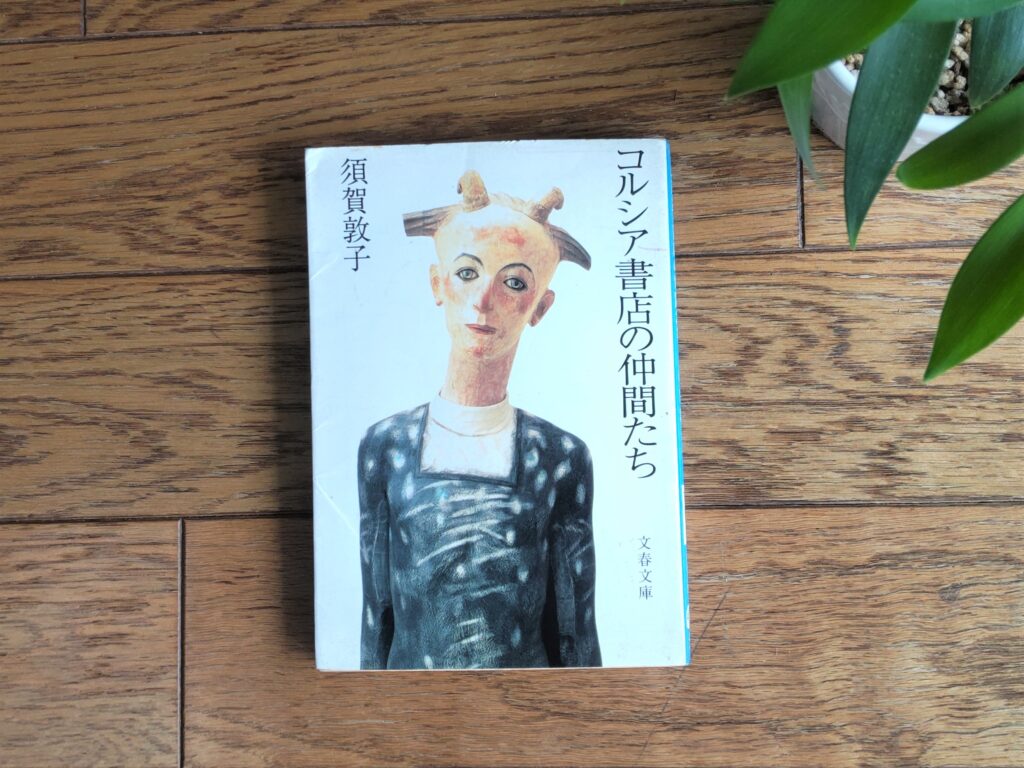
このようにして、書き留めたノートはたまり、感想やアドバイスを書いたお手紙も何通かいただいた。
ご本人が亡くなられた今、大事な形見の品となっている。
きっと、最後の最後まで処分することはできないだろう。
皆さんにも、同じように、たとえ終活でも無理というものがあるでしょうか。
それはなんですか。また、また、どこまでもっていきますか。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。











コメントを残す