玉木屋の女房〈10〉
「ああ、こりゃあ、いい版木だ」
多江が蔦重の耕書堂に行った翌日、早速店の手代が版木を届けにきた。作治は早速仕事に取りかかった。良い下絵と版木があればそれだけで作治は満足なのだ。そんな姿を見ながら、
「お手柄だよ。多江」
ゆらは満足げに言った。それにしてもゆらは娘の多江にとって、いつまでも怖い母だった。
数年前、多江がまだ少女の頃に、店にやって来たお静さんが、ゆらがいないと見て取ると、すーっと多江のそばまで来て耳打ちした。それは、父が亡くなって間もなくの頃だった。
「あんた、平気かい」
多江は驚いてお静の顔を見つめた。
「いえね、心配してるのよ。なさぬ仲の母と娘が二人っきりで一緒に住んでるって言うのがね。町内の人もみんな気になってるのよ。何かあったら困るって。何しろ、ゆらさんは今じゃ、貞女だって顔をしてなさるけど、元吉原の遊女で、しかも好きな人ができて、心中までしようとしてたのを、あんたの父親、清吉さんが二百両で身請けしたっていうのさ。ほら、あんたのところの玉木屋も、その頃は羽振りが良かったからさ。今ではすっかり見る影もない家の中で、清吉さん亡き後、なんで生さぬ娘の面倒を見るもんか、って。だから、多江ちゃんの話を聞いてきてくれって頼まれたのよ、顔役さんに。ほら町内で何かあったら困るって」
多江は笑ってこたえた。
「おばさん、ありがとう。でも大丈夫。おっかさんは、いつも、大事にしてくれてるから。あたしは、自分よりあんたの身のほうが、可愛いんだよって、いつもいってるわ」
「まあ、口ではなんとでも言えるでしょうからね」
お静はそういうと、ちょっと拍子抜けした感じで帰って行った。
間もなくゆらが戻ってきたが、お静が留守の間に来ていたことも、聞いた話のこともひと言も伝えなかった。言わない方がいいような気がしたからだ。


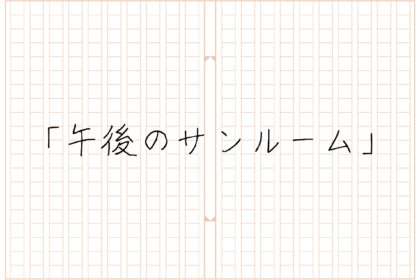







コメントを残す