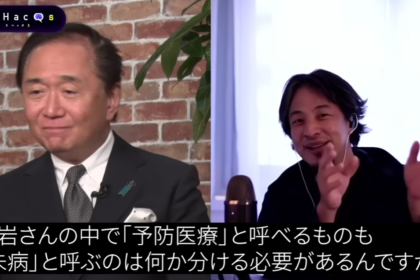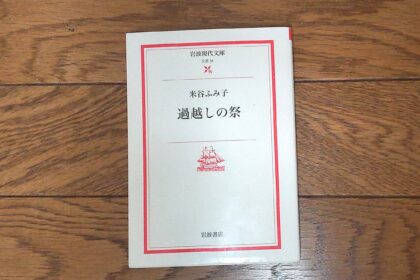道長と紫式部はほんとに相思相愛だったのか? それとも妾?「輝く日の宮」では道長が寝物語などで自分の体験を提供したのではとも #光る君へ
こんにちは、ゆきばあです。毎日ブログを更新しています。

幻の巻 かがやく日の宮
丸谷才一氏の小説に「輝く日の宮」という作品があります。女性学者の安佐子を主人公に、源氏物語の構成や、道長と紫式部の関係などをミステリータッチに描いたものです。
ちなみに「輝く日の宮」とは藤壺の宮のこと。
「源氏物語」には本来、源氏と藤壺の宮との逢瀬を書いた巻があったのではないか、それがどこかで消失したのではないか、という説があります。
順序として、桐壺 → 帚木 なのですが、この間に、藤壺との逢瀬を描いた「輝く日の宮」の巻があったという説です。もともとは、藤原定家が「かゝやく日の宮 このまきもとよりなし」と書いたのがはじめみたいです。
紫式部は道長の妾だった?
ところで、二人は主人と使用人の関係だとか、いや紫式部は、妾だったとか愛人(召人)だったとかいわれています。丸谷氏は、この小説の中で、二人はもちろん恋人(?)同士だった。そして、中に書かれているさまざまな恋の体験やエピソードは、寝物語にでも道長自身の体験を話したのではないかと、語っています。
そして、かなり道長の考えを入れたり、修正したりしたのではないかと。つまり、作家と編集者みたいな関係だったってことでしょうか?
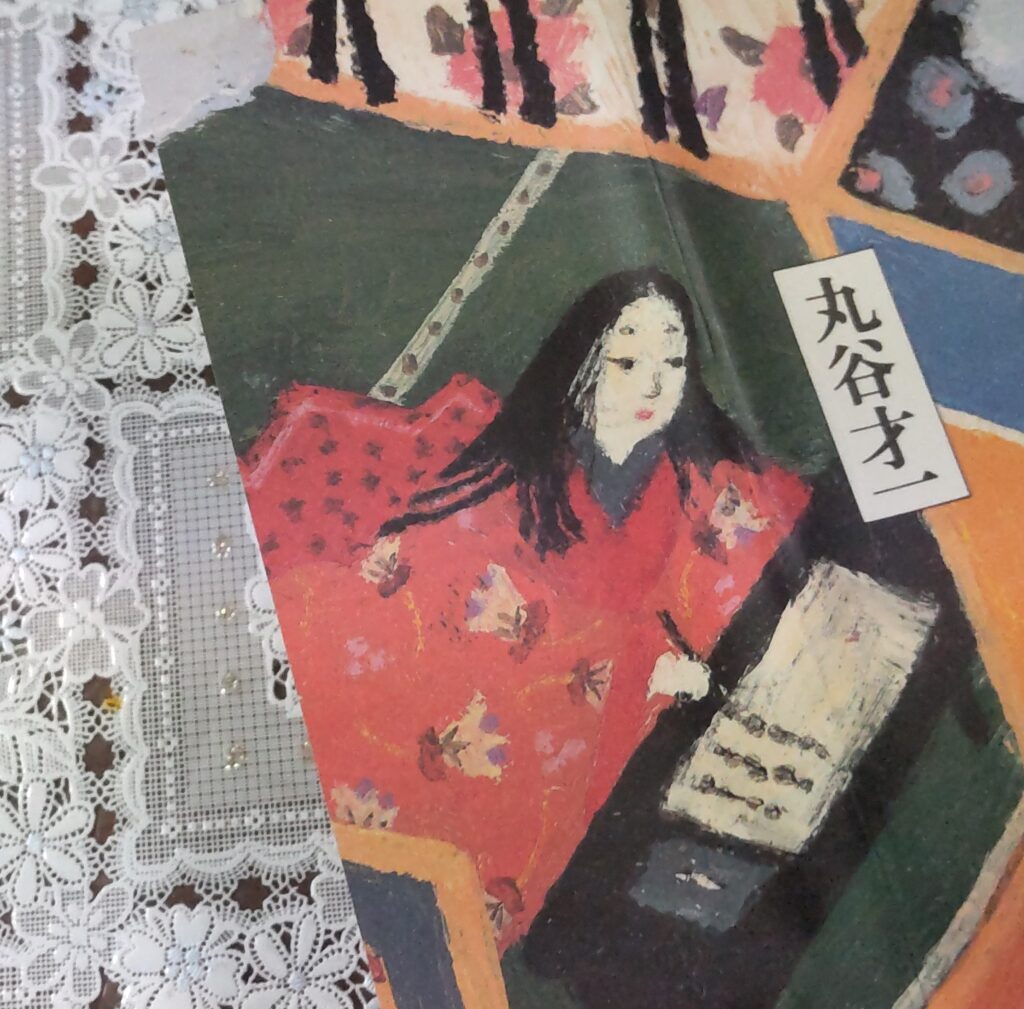
今回の「光る君へ」ではさらに踏み込んでいて、幼い頃からの心の友であり、悲惨な体験を共にした両想いの関係となっていますね。この互いへの熱い思いが、今後執筆される「源氏物語」に、どう反映されていくのかとても楽しみです。
また先ほどの「かがやく日の宮」の巻ですが、丸谷氏の小説の中では道長が、「完全すぎるより、ぼやけていたほうがいいよ」といって紫式部の目の前で火桶にくべて燃やしてしまうのです。
紫式部も、苦労して書いたものを焼かれるのはつらいのですが、「やはりそれで良かったかも・・・」と納得する、展開になっています。
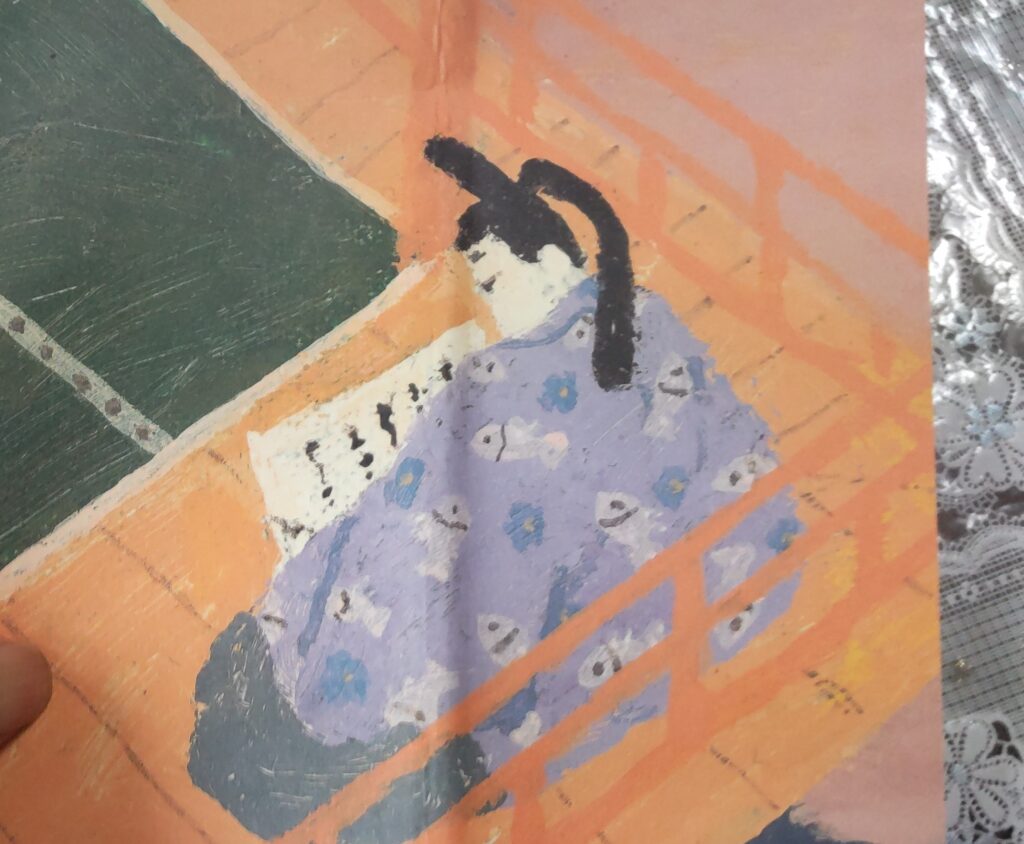
「不完全なほうがむしろいい」という言葉ですが、これは芸術全般や人生そのものにもいえる気がして心に残っています。
こんなちょっとした苦みや後悔も、人生の醍醐味といえるのかもしれませんね。
今日も最後まで読んでくださりありがとうございました。ほかにも日々の思いを書いていますので、目を通していただけましたら幸いです。